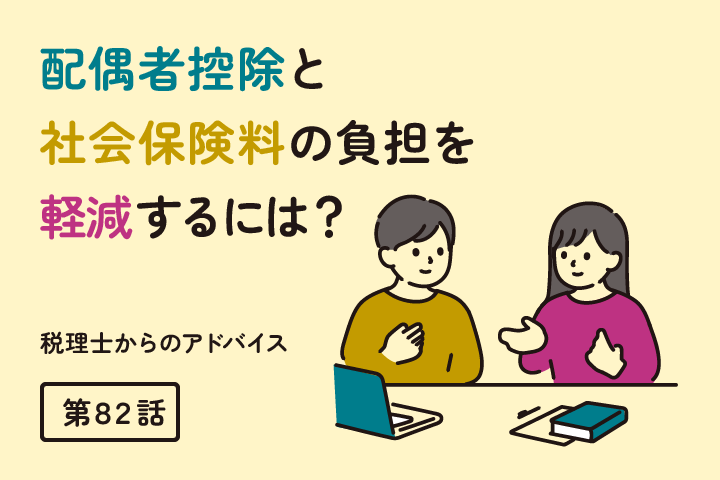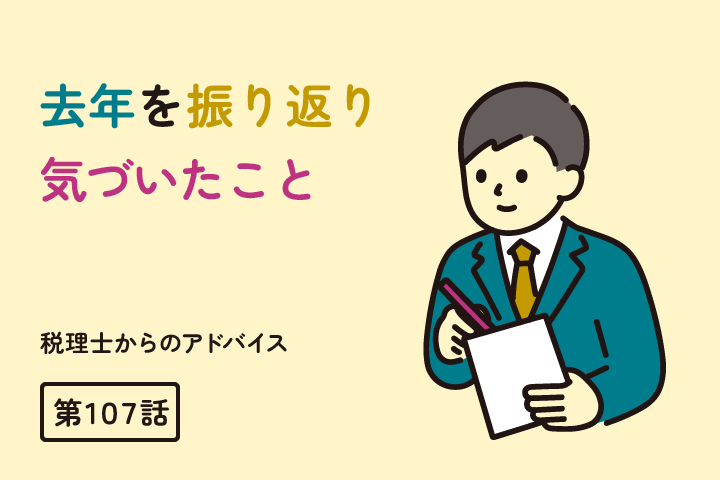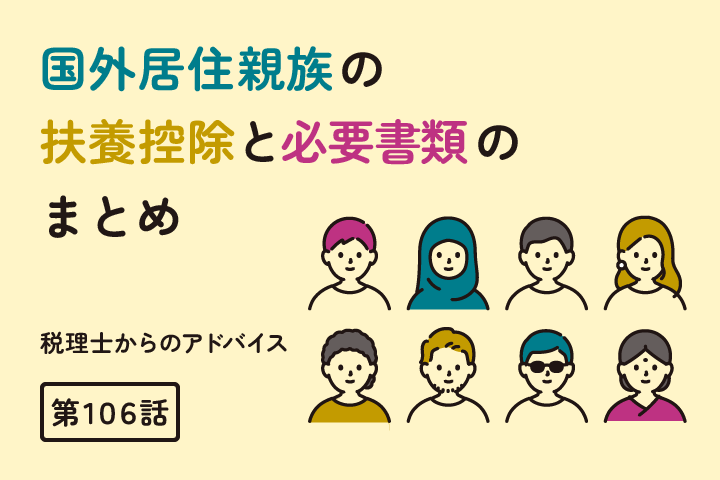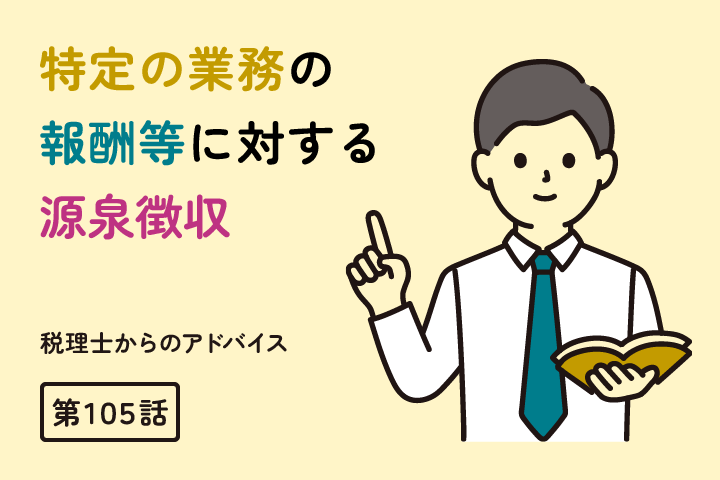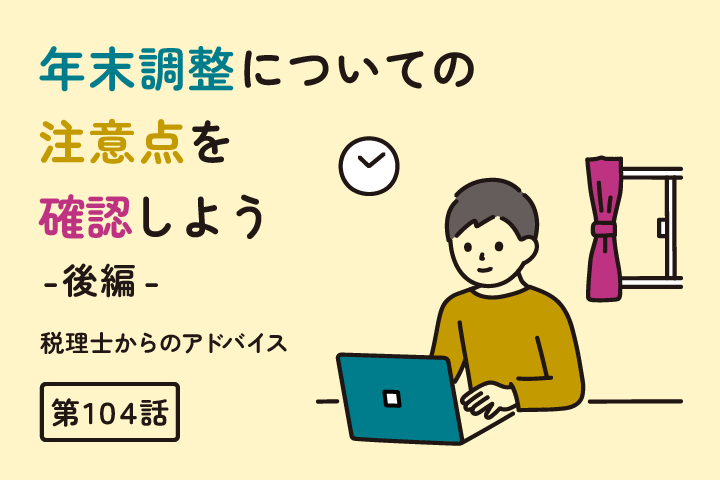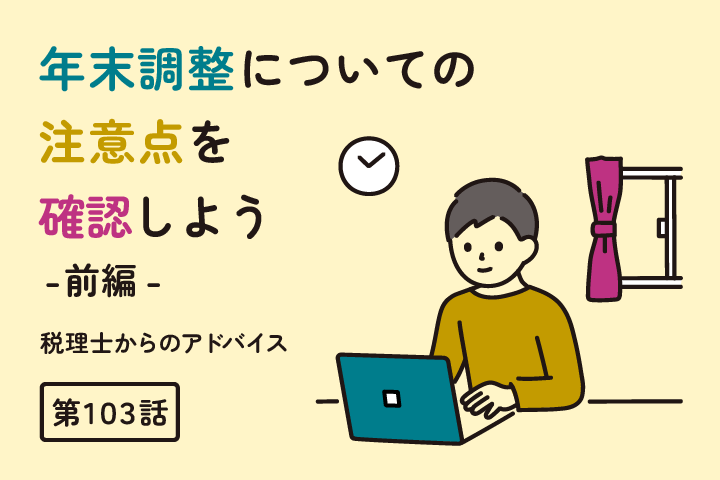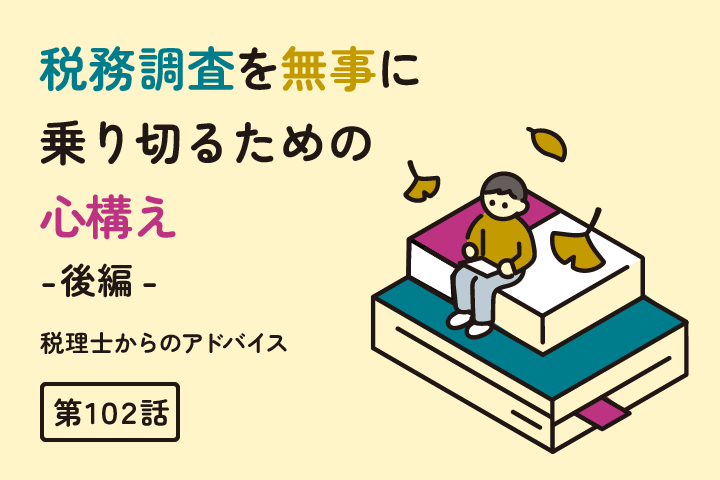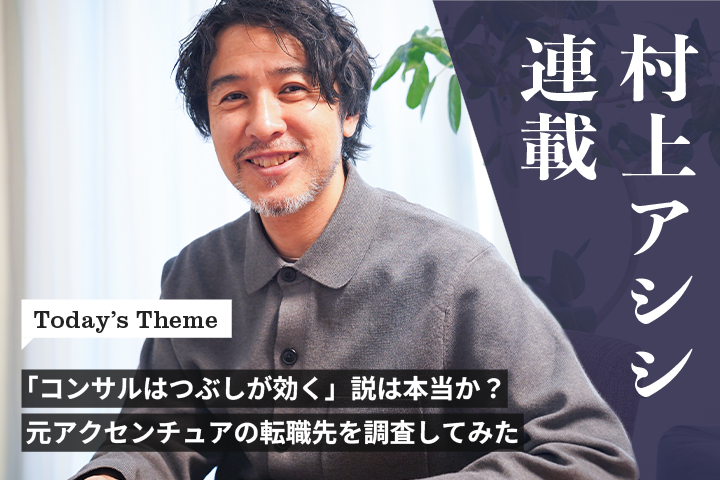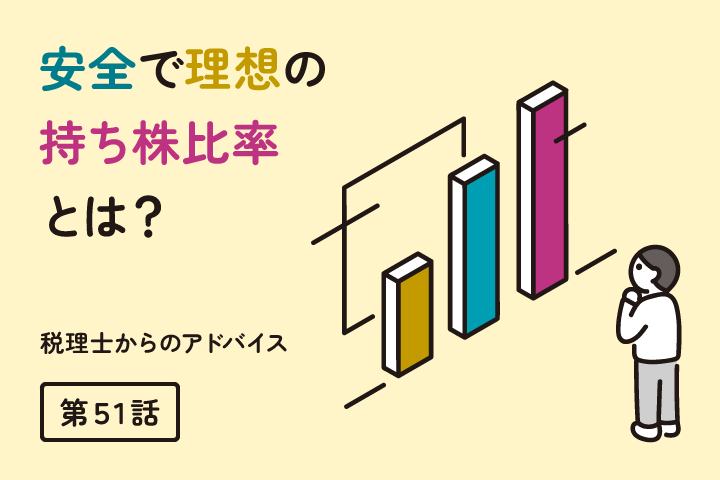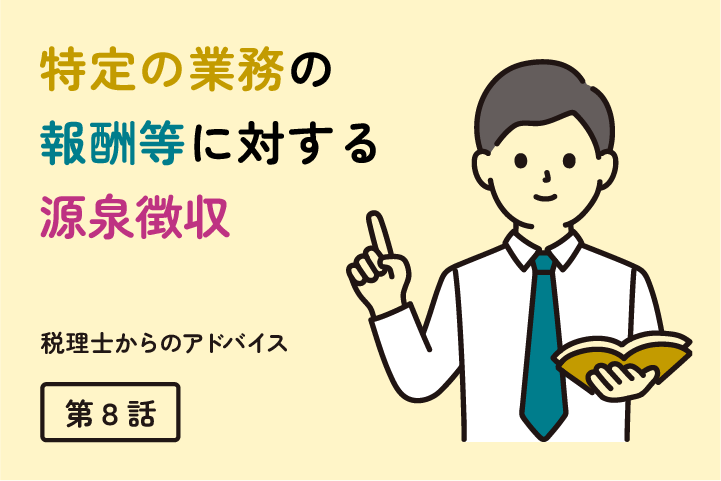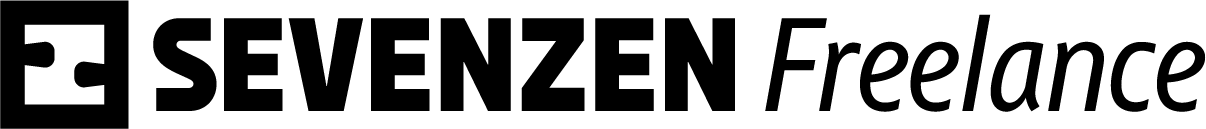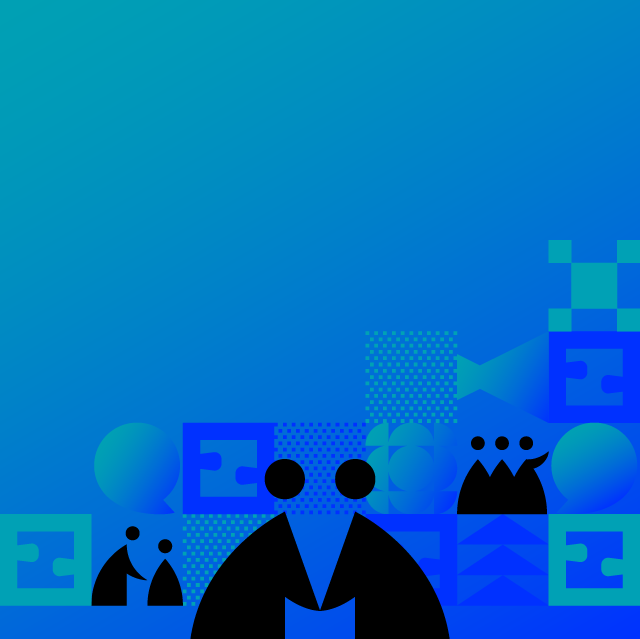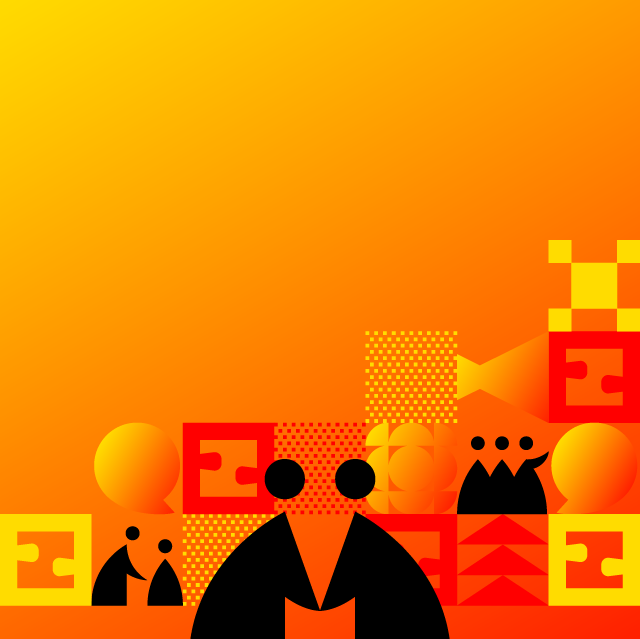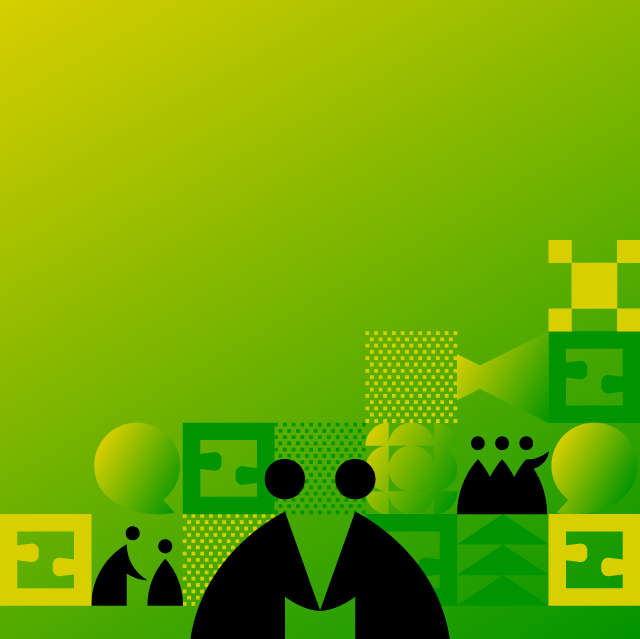配偶者控除
最初に配偶者控除について書いていきます。
対象は、自己の妻又は夫で12月31日現在同一生計配偶者である者(合計所得金額が1,000万円超である納税者の配偶者を除く)
同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が48万円以下の者(青色事業専従者や白色事業専従者を除く)
生計を一とは、原則同居であるが、別居でも、例えば夫が妻へ仕送りをしている場合には“生計を一”に該当する。生活の面倒を見ているという事。
合計所得金額1,000万円超については、ざっくり説明すると給与所得のみの方であれば、年収1,120万円超の方を言います。
配偶者控除が受けられる例は、
夫給与の年収800万円で妻(30歳)の給与年収30万円
夫の合計所得金額は800万円―190万円(給与所得控除額)=610万円
妻の合計所得金額は30万円―30万円(給与所得控除額)=0円
配偶者控除38万円が受けられます。
(配偶者が12月31日現在70歳以上の場合には、48万円となります。)
配偶者特別控除について、簡単に説明をします。
最近は共働きが多くなりました。
夫給与の年収800万円で妻(30歳)の給与年収125万円
夫の合計所得金額は800万円―190万円(給与所得控除額)=610万円
妻の合計所得金額は125万円―55万円(給与所得控除額)=70万円
この場合、配偶者控除は受けられないですが、配偶者特別控除は受けられます。
配偶者控除が受けられなくても配偶者特別控除が受けられる場合があるので確認をしてください。今回の場合は38万円の配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除の金額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額で配偶者特別控除額が決まります。配偶者の合計所得金額が133万円超となると配偶者特別控除額は0円となります。
実務上、妻の健康保険料を支払わない範囲内で妻の所得をセーブする場合が多いです。

社会保険料
全国健康保険協会の社会保険の被扶養者要件は、年間収入130万円未満の妻となります(妻が60歳以上の場合は、180万円未満)。「130万円」の壁と言われています。ここでは収入なので給与のみであれば、年収で判定します。
例えば、妻がアルバイトで、給与の年収100万円で副業の事業収入が20万円であれば、100+20=120万円で被扶養者となれます。
(事業収入は、収益―費用となります。青色特別控除前の金額となります。)
実務では、妻の税金負担や社会保険料の負担が無い範囲内で働く場合もあります。
従業員が100(令和6年10月以降は、50)人以下の会社に勤務するアルバイトの年収が130万円を超えていても、一時的なものであれば、継続して配偶者の被扶養になることが出来ます。勤務先の会社が、一時的な収入変動に係る事業主の証明書を健康保険組合へ提出すれば大丈夫です。
夫800万円妻700万円の給与収入の場合には、今回の配偶者控除や配偶者特別控除は受けられません。社会保険も妻が加入となります。しかし、医療費控除については、生計を一であれば、課税所得の大きい夫に妻の医療費を合算して申告すると節税となる場合があります。
昔と違って働き方も変化しています。ご自身のライフステージによって税金や社会保険料の負担を減らしながら仕事をする。今回のテーマがその参考になれば嬉しいです。
それでは。良い一日を!!