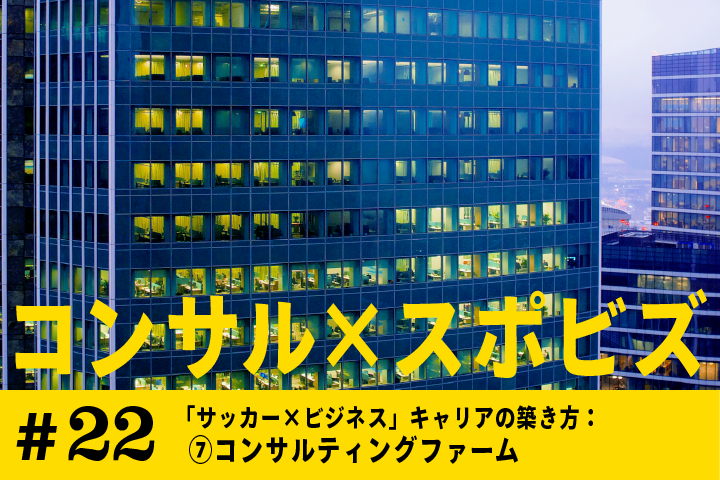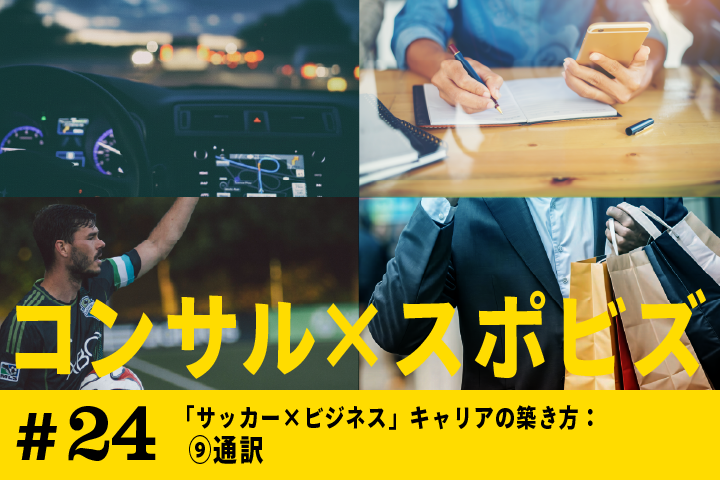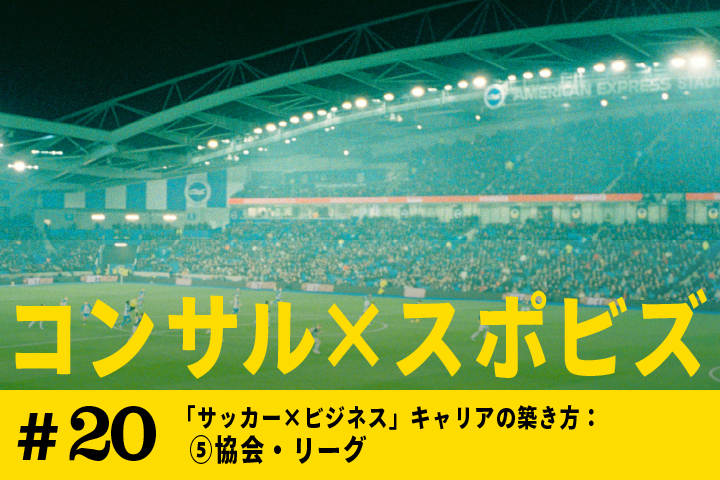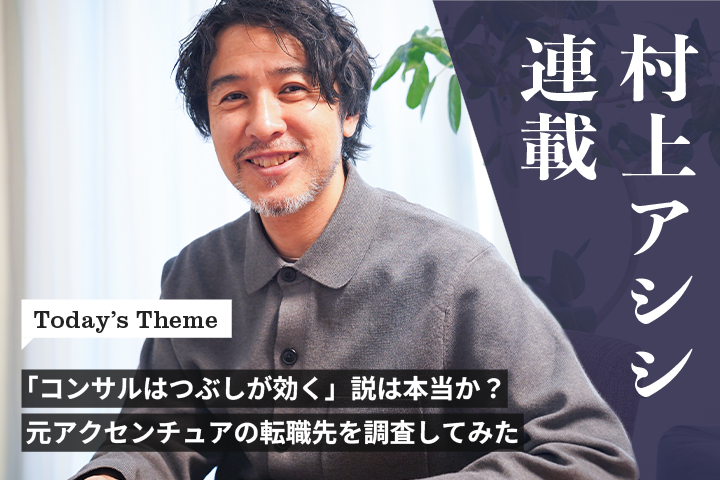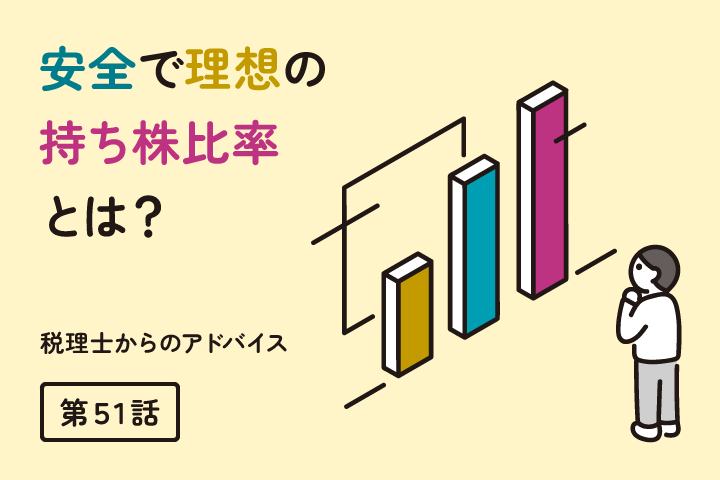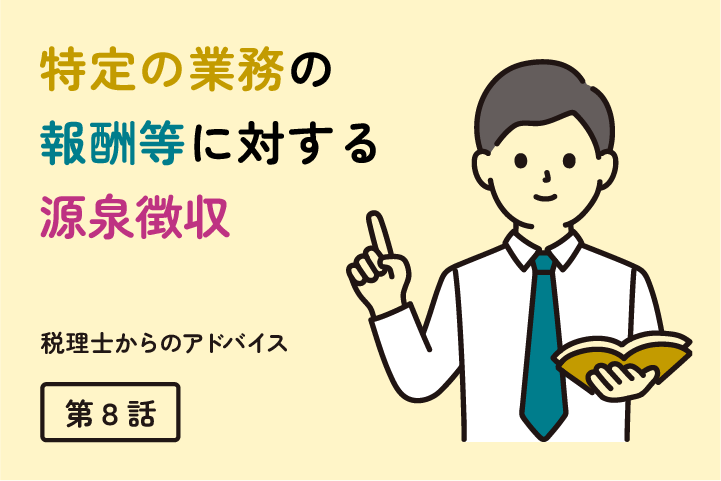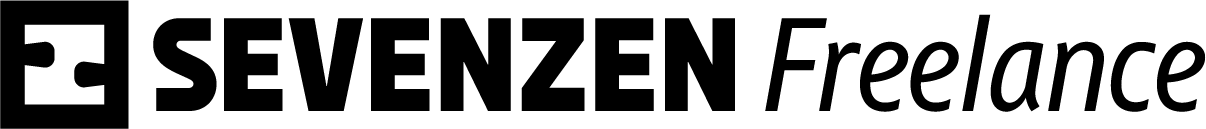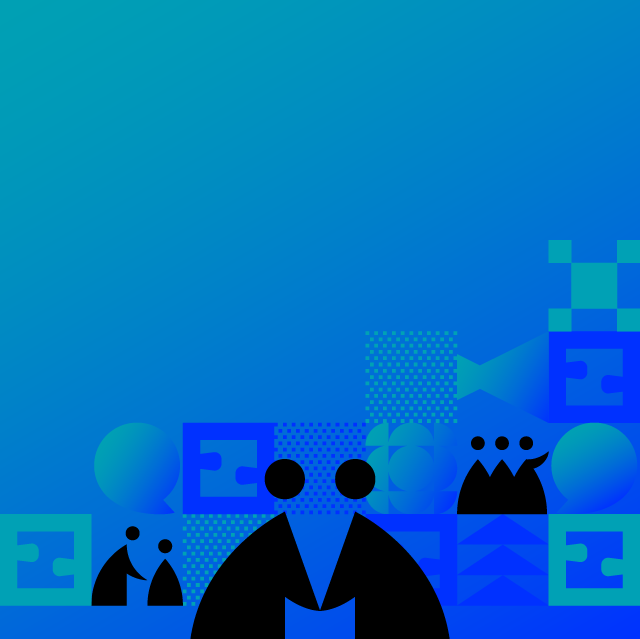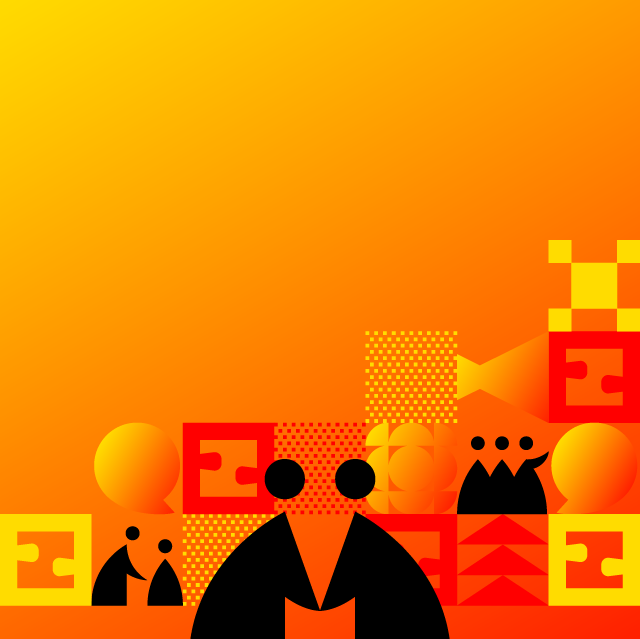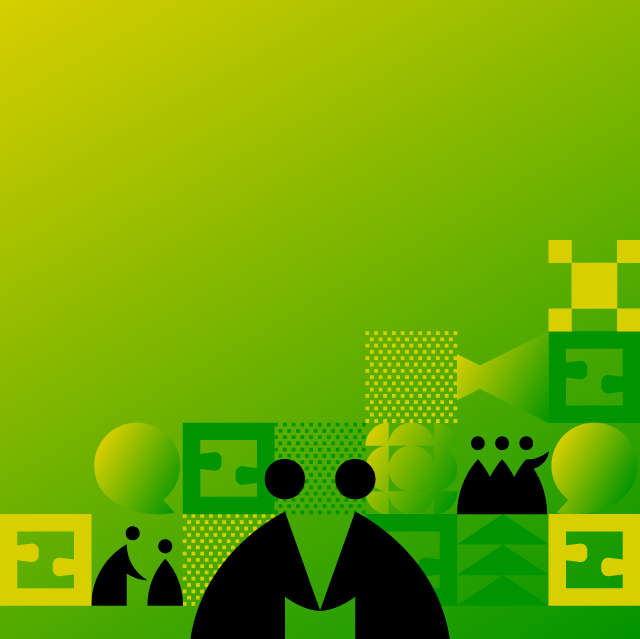「サッカー×ビジネス」キャリアの築き方の連載において、第1-6回目までは、サッカービジネスのど真ん中に位置する「スポーツ部門(強化部)」とそれに直接的な影響を与え得る周辺産業におけるキャリアについて解説しました。
今回からは3回に分けて、自分自身のこれまでのキャリア(大学の外国語学部⇒コンサルティングファーム⇒個人事業主として独立・プロサッカークラブと契約)を踏まえ、特に読者の皆様に経験則をお届けしたい「コンサルティングファーム」「フリーランス/個人事業主」「通訳」というキャリアについてご紹介いたします。
(私のこれまでのキャリアについては、こちらの記事でもお話しています。)
第7回目は「コンサルティングファーム」について、ご紹介いたします。
本題に入る前に、本連載の「前提」を振り返ります。
※本連載の全ての記事において、冒頭に「前提」を明記します。記憶が新しい方は読み飛ばしていただいて構いません。
連載の前提
■内容
「サッカー×ビジネス」というキャリアの築き方について、スポーツ部門(強化部)の周辺ステークホルダーから考えられる職種、就職の方法、得られる機会、注意点、ネクストキャリアの可能性など
■ターゲット
国内外の有名大学を卒業予定で将来はサッカー/スポーツビジネス業界でキャリアを築いていきたい学生、または、その延長にいる若手社会人
■コンセプト
単なるお仕事図鑑ではなく、スポーツ部門にいながら感じた現場のありのままの情報を届けること(情報の全体感より深さを優先)
上記を前提として、本文をご一読いただけると幸いです。
「サッカー×ビジネス」のキャリア:⑦コンサルティングファーム
コンサルティングファームにおけるスポーツビジネスの盛り上がり
私がデロイトトーマツコンサルティングに所属していた2016年から2020年までは、コンサルティングファームがスポーツビジネス支援を行うケースはごくまれでした。その中でも、当時の記憶を辿るとデロイトはいち早くスポーツビジネスに着目していた印象です。当時の両社代表同士の関係性が前提にありつつも、私が入社したタイミングではすでにFC今治とのプロジェクトが進行していました。また、ほどなくしてJリーグやJFAへの支援も本格化しました。ただし、これらはそこまで採算性が高くなく一定の投資領域だったと推察しています。それよりも、数少ないスポーツビジネスへのコンサルティング機会でしたが、クライアントとファームの双方にとって事業性が比較的高いプロジェクトがあったとすれば、一般的な事業会社の支援がメインでした(私自身も、メディア業界で2社のスポーツビジネス領域における新規事業開発ご支援に携わりました)。
しかし、近年コンサルティングファーム各社がスポーツビジネス領域への進出を強めています。背景として、各社が当該市場の成長性や社会的意義に注目し、本格的な事業領域として着目していることが挙げられるでしょう(一定投資の側面はありつつ)。個人的にも、AIが日進月歩で進化し、ますます余暇時間の有効活用が見直され、リアルエンタメ領域の価値が再認識されている中で、スポーツが持つ事業としての潜在性は高いものと感じています。また、スポーツが地方創生・地域活性化や社会課題(SDGsやサステナビリティ領域)との親和性が高いことも背景にあると考えています。
よりマクロな視点で検証してみると、2015年にスポーツ庁が設立され、2012年時点では5.5兆円だったスポーツの市場規模を2025年には約15兆円に拡大する目標が掲げられました。この2015年から2025年という期間は、ちょうど私がコンサルティングファームに入社し、スポーツビジネスの黎明期を過ごし、パンデミックやAIの急進化によりリアルエンタメの価値が再認識され、スポーツの事業性が高まり始めてきた(=コンサルティングファームも注目し始めた)タイミングと重なります。スポーツ庁による目標設定から気づけばはや2025年になりました。おそらく市場規模15兆円の達成には届かないでしょう。それでも、日本のGDP規模でいうと、欧米におけるスポーツビジネスの市場規模水準に到達する大きな余白やポテンシャルがあると世の中が期待しているため、この10年間でコンサルティングファームに限らずIT企業も含め、様々な事業者がスポーツビジネス領域に着手し始めているものと感じます。
コンサルティングファーム各社によるスポーツビジネスへの取り組み事例
コンサルティングファームの中でも、特にクライアントの業界(インダストリー)も支援領域(コンピテンシーまたはソリューション)も、ともに幅広い総合ファームの取り組みが豊富です。
デロイトでは、コンサルティング部隊(デロイトトーマツコンサルティング)が、前述のFC今治との取り組みを2015年から推進していました。2020年からはデロイトトーマツグループ全体で「ソーシャルインパクトパートナー」として、マーケティングや新スタジアム構想、SROI(Social Return on Investment 社会的投資収益率)可視化など様々なプロジェクトを行っています。他にも、2017年からJリーグのサポーティングカンパニーとなり、経営戦略やデジタル戦略の策定及び推進を支援したり、デロイト本社がヨーロッパクラブの財務分析レポートである「デロイトフットボールマネーリーグ」を発表していることから、日本ではFAS部隊(デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー)が中心となって「Jリーグマネジメントカップ」を公開したりするなど、早くからスポーツビジネス支援に取り組んでいます。
デロイトに次いで近年スポーツビジネス領域に特に力を注いでいるのがKPMGでしょう。2020年よりJリーグの湘南ベルマーレとオフィシャルクラブパートナー契約を締結し、「デジタルイノベーションパートナー」としてデジタル戦略の立案及び推進を支援したり、2022年からは地域振興×SDGsに取り組んだりしています。他にも、2023年から女子プロサッカーリーグであるWEリーグの「ソーシャルインパクトパートナー」、2024年からはJリーグの「気候アクションパートナー」になり、リーグ・クラブ双方と協業することで、特にスポーツを通じた社会課題の解決に投資しています。
いわゆる「BIG4」と呼ばれる総合ファームの中では、上記以外にも、PwCが2021年よりJリーグの川崎フロンターレとオフィシャルトップパートナー契約を締結し、企業ロゴの広告露出に限らず、戦略策定の支援や各種イベントを通じたマーケティング活動、2024年からはアカデミー選手の競技データ管理に向けたプラットフォーム導入及びその活用支援などを行っています。また、EYは2022年よりプロバスケットボールリーグであるBリーグとサポーティングカンパニー契約を締結し、人材や社会課題(SROI可視化を含む)領域を中心に支援を行っています。
また、日系の総合ファームの中では、特にアビームが実績豊富であり、スポーツ&エンターテインメントという切り口でインダストリーチームを保有しています。Jリーグのモンテディオ山形の経営支援や、スポーツ庁、スポーツ競技団体、スポーツスタートアップなど様々なクライアントの支援実績を残しています。
総合ファーム以外にも、大手外資戦略ファームであるカーニー(旧ATカーニー)が2024年よりJリーグとサポーティングカンパニー契約を締結し、2023年から取り組む経営戦略の策定及び推進支援をより強固にしています。また、日系の戦略ファームでは、フィールドマネージメントがブティック系ファームながら日本で有数の知名度と実績を残しています。例えば、Jリーグ及び横浜ビー・コルセアーズ(Bリーグ)への役員派遣を始めとし、リーグ・クラブやオーナー企業など様々なクライアントに対する上流支援を行っています。

コンサルティングファーム×スポーツビジネスのキャリア
スポーツビジネスに注力する総合ファームは、毎年三桁規模で大量の新卒一括採用をしているため、「コンサルティングファームに入社する」という意味では、就職活動の成果次第ではそこまでハードルは高くないと言えます。ただし、配属先は個人の希望のみでは決められないため、望まないインダストリーやコンピテンシー部門に配属される可能性は常に存在します。一方で、中途採用の場合は「スポーツビジネス」チームなど、特定領域に絞った応募が可能ですが、募集枠自体はそれほど多くありません。ポジションが空くのは年度ごとの事業計画や離職状況次第なので、入社できるかどうか自体がタイミングや縁による要素が多くなります。特に、前述のフィールドマネージメントなど大手ではなく新卒一括採用も行っていないファームであれば、中途入社が現実的な選択肢となります。
したがって、「コンサルタントとしてスポーツビジネス案件に携わることを最優先するなら中途採用、まずはコンサルティングファームに入社することが目標なら新卒採用」という判断が現実的でしょう。とはいえ、人が商品であるコンサルティングファームでは、メンターや上司との1on1面談が頻繁に設けられており、与えられた場所で常に成果を出しながら自らの希望を伝え続ければ、その願いを上司や会社が叶えてくれる機会は十分にあります。コンサルタントになりスポーツビジネスに関わりたいのであれば、前段でご紹介したスポーツビジネス案件が豊富な総合ファームを中心に新卒入社を目指し、スポーツビジネスのプロジェクトに配属される機会を待ちながら自己研鑽するキャリアは、たとえ希望通りにならなかったとしても、自らの経験を振り返っても必ずや財産になると考えています。
現在のコンサルティングファームで働く上での注意点
米国を中心とするグローバルでは、過剰な大量採用トレンドの反動を受けて、一部大手ファームが人員削減に動き始めたというニュースも聞かれるようになりました。日本ではまだ採用意欲が高い状況ですが、米国発のトレンドが数年遅れで波及するのはコンサル業界の常です。採用や昇進の規模が縮小に転じるリスクは頭の片隅に置いておくべきでしょう。
さらに、働き方改革の浸透により労働時間は年々抑制傾向にあります。従来の「修羅場で鍛えられる濃密な徹夜プロジェクト」を期待する若手にとっては、物足りなさを感じる場合もあるかもしれません。大量採用ではありがちな現象ですが、一時期と比べると人材の質が多様化しているとも言われており、実態が伴わなければ、「有名コンサルティングファームでの経歴が履歴書に書かれていれば次のキャリアは安泰」ということにはならないでしょう。
ポストコンサルティングファーム×サッカービジネスのキャリア
コンサルタントのネクストキャリア(俗にいう「ポストコンサル」)は多岐にわたります。新卒から同じファームに居続ける、または、転職で職位アップを繰り返すことでパートナーまで昇り詰めるルートは意外とまれです(おそらく、いわゆるファームに所属する全コンサルタントの10%にも満たない確率)。多くのコンサルティングファーム出身者は、ポストコンサルのキャリアとして、PEやVCなどファンドへの転職、クライアントワークでナレッジとスキルを培った業界の事業会社における経営戦略や経営企画部への転職、中小企業やスタートアップへのCxO転職、あるいはフリーコンサルタントとしての独立や自らやりたい事業での起業などを選択する傾向にあります。
ことサッカービジネスにおいては、放映事業主や広告代理店、メーカーなど一般的なスポーツビジネス関連の事業会社を主流に、JリーグやJFAなどの競技団体、プロクラブへの転職などが一般的な印象です。ただし、プロクラブは契約形態が正社員ではないケース(契約社員や業務委託)や報酬が高くないケースも散見され、コンサルティングファームからの転職という意味では、正社員として報酬の下げ幅も致命的にはならないJリーグ・JFAへの転職者の方が多い印象です。
私自身は、正社員でなくてはならないという強いこだわりはなく、むしろコンサルティングファーム退職後数年で起業したいと考えていたので、業務委託でまずは個人事業主として携わる選択肢はむしろ希望通りでした。その中で、コンサルティングファームを離れ、プロクラブの現場(特に、強化部)からサッカー業界の業務に関われたことは、非常に貴重な学びとなりました。コンサルタントによく向けられる「現場感がない」という偏見を払拭したいなら、JリーグやJFAも良い選択肢ではありますが、より現場でお客様の反応を感じられるクラブでのキャリアの方が面白いのではないかと個人的には思います。
私の知る限りでは、JリーグやJFAにはデロイトやその他BIG4ファーム出身者が少なからず在籍しています。一方で、クラブ側にはまだ人材の流入が少ない印象です。職種としては、これらリーグやクラブにおける経営戦略や企画、海外事業開発、財務を始めとする管理(強化部も含む)などが、サッカー業界におけるポストコンサルの主なキャリアでしょう。
転職のタイミングとしては、サッカービジネス業界を専門としてキャリアを登りたいのであれば、コンサルタントやシニアコンサルタント職位での転職(一般的にはおよそ3-5年経験した後)が適切だと考えています。マネージャークラスに昇格した後(一般的には入社後およそ5-7年)では、報酬の差が大きくなりすぎたり、家庭もできていたりするケースもあるため、転職に踏み切りづらくなると考えています。
さいごに
コンサルティングファームで培ったビジネス基礎力があれば、サッカー業界や広くスポーツビジネス業界でも活躍できると確信しています。将来サッカービジネス業界で活躍したいが新卒入社ではないと考えている方にとっては、以前ご紹介した「サプライヤー」「親会社」と同様に、研修制度が確立されており大小様々なプロジェクトに関われるコンサルティングファームは推奨できる選択肢でしょう。中途の方にとっても、ビジネスを体系的に学びながらコンサルティングの現場で応用力を身に付けるには、もってこいの環境だと思います。特に、サッカービジネス業界に転職したいが、現在は事業会社で全く異なる業務をしているなどの悩みがあれば、一度コンサルティングファームで汎用的なスキルを身に付け、キャリアをずらしていく「経由地点」としても悪くない環境です。ただし、新卒であろうと中途であろうと、第三者の立場ではなく主体者として業界で判断力や実行力を磨きたいのであれば、最終的なキャリアの目標はぶらさずに、コンサルティングファームにおける高給に目をくらますことなく、自らの信念にもとづき適切なタイミングで業界に飛び込む勇気を持って欲しいと思います。
次回は、⑧「フリーランス/個人事業主」についてご紹介します。