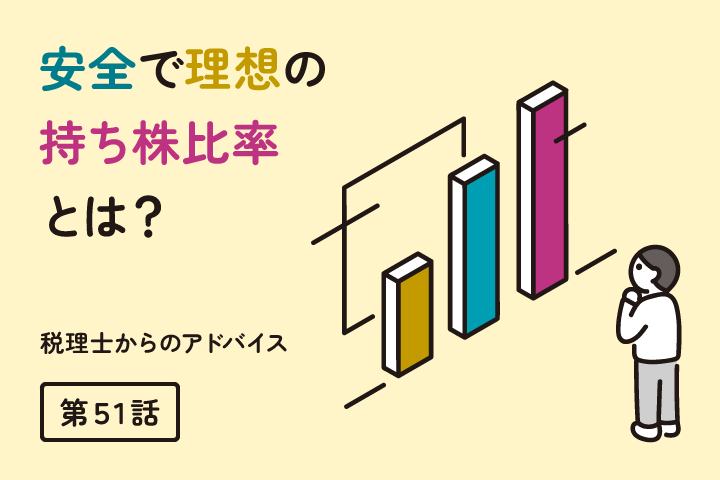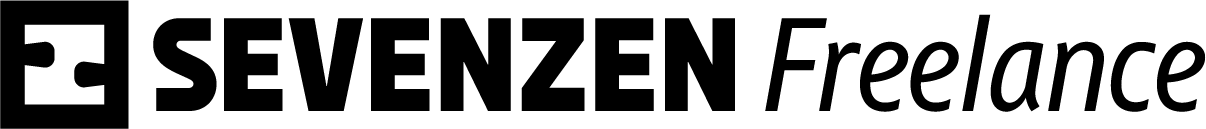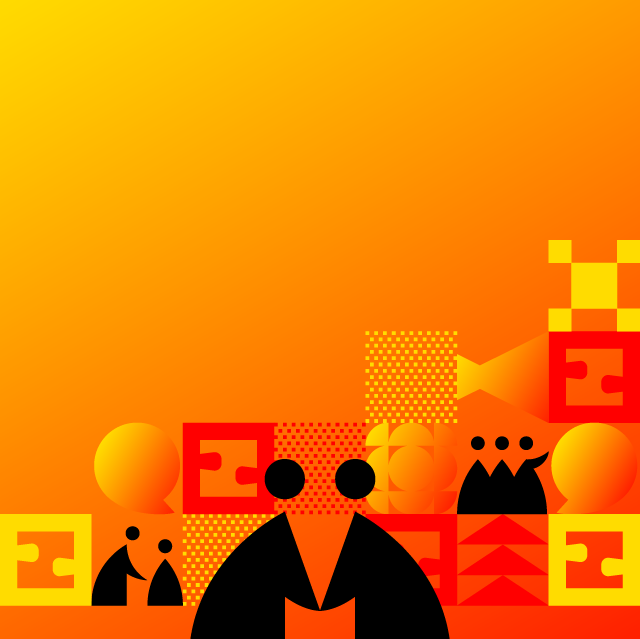「サッカー×ビジネス」キャリアの築き方、第6回目はスポーツ部門及びクラブの経営を左右する「親会社」について、ご紹介いたします。
本題に入る前に、本連載の「前提」を振り返ります。
※本連載の全ての記事において、冒頭に「前提」を明記します。記憶が新しい方は読み飛ばしていただいて構いません。
連載の前提
■内容
「サッカー×ビジネス」というキャリアの築き方について、スポーツ部門(強化部)の周辺ステークホルダーから考えられる職種、就職の方法、得られる機会、注意点、ネクストキャリアの可能性など
■ターゲット
国内外の有名大学を卒業予定で将来はサッカー/スポーツビジネス業界でキャリアを築いていきたい学生、または、その延長にいる若手社会人
■コンセプト
単なるお仕事図鑑ではなく、スポーツ部門にいながら感じた現場のありのままの情報を届けること(情報の全体感より深さを優先)
上記を前提として、本文をご一読いただけると幸いです。
「サッカー×ビジネス」のキャリア:⑥親会社
「企業クラブ」と「市民クラブ」
まず親会社を理解するための前提として、Jリーグ所属クラブの経営母体をパターン分けして理解する必要があるでしょう。歴史的な変遷を踏まえて大別すると、Jクラブの経営母体は以下の3パターンに分かれます。
(1)実業団の保有企業
(2)独立企業
(3)オーナーチェンジ
Jリーグというプロサッカーリーグが1993年に開幕する前、その起源となる多くのサッカークラブは、企業サッカー部(=実業団)の位置づけにありました。Jリーグ発足時に加盟したいわゆる「オリジナル10」も、一部を除き多くが実業団由来のチームでした。その後もJリーグが興行的に盛り上がりを見せる中で、オリジナル10以外にもいくつかの実業団がプロ化することで、J1リーグ所属チームが増えたり、その下位カテゴリーであるJ2リーグという受け皿が発足したりしました。このような経緯から、いくつかのJクラブは、実業団時代から継続して今でも元々の所属企業が株式の過半数以上を保有し、その子会社として経営されています(1)。代表格で言えば、トヨタ自動車のサッカー部を母体に発足した名古屋グランパス、松下電器(現パナソニック)サッカー部由来のガンバ大阪などがあります。
Jリーグが成長するにつれて、後発のクラブも多様化していきました。いくつかのサッカークラブは、実業団由来ではない独立運営の「街クラブ」「市民クラブ」として発足し、アマチュアリーグを勝ち抜きプロのJリーグに参入します。街クラブの運営会社として、どこの企業にも過半数以上の株式を売却せずに経営してきた場合、特定の親会社を持たず地域の企業や行政などが薄く株式を保有する「独立企業」として分類されます(2)。代表格で言えば、2024年にJ1昇格プレーオフを勝ち抜き、クラブ史上初のJ1昇格を決めたファジアーノ岡山(運営会社は株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ)が挙げられます。
このような、「企業クラブ」(1)と「市民クラブ」(2)という2つの大きな変遷に加えて、元々サッカー部を保有していた企業が事業整理としてクラブ運営を担う子会社を売却し親会社が変わったもの、もしくは、独立採算では経営が成り立たず or さらなるサッカークラブとしての成長を意図した増資のために、他企業に事業譲渡されたものが、別親会社へのオーナーチェンジに分類されます(3)。最近の事例では、マツダサッカー部を起源とするサンフレッチェ広島が2023年7月に第三者割当増資を行い、それを引き受けた株主の一角であった株式会社エディオンが保有株式を約47%から約76%に増やし、同クラブを連結子会社化しました。さらに最近だと、2025年1月末までに、北海道コンサドーレ札幌が「白い恋人」で有名な石屋製菓から増資を引き受け、同社の子会社になることが予定されています(※報道ベース)。なお、これらの例のように、オーナーチェンジの流れは、スポンサードする過程で少数株式を保有していたスポンサー企業が、出資額を増やして株式の過半数を引き受けるケースがよくあります。保有元企業が譲渡先を選定するにあたり、主要スポンサーとして両社が互いをよく理解している企業の方が、サッカークラブの歴史や文化、サポーターなどが尊重され、安心して運営を任せられるためでしょう。
■ memo:
サンフレッチェ広島についてのソースはこちら
コンサドーレ札幌についてのソースはこちら
近年のオーナーチェンジの特徴
一般的に、プロサッカークラブはプロチームに投資をすればするほど強くなる傾向にあるため、特にトップリーグであるJ1リーグに昇格したいクラブや是が非でも残留したいクラブは、自助努力で獲得できる財力以上の費用を費やし、赤字分については親会社に補填してもらうという運営手法を採用する場合があります。親会社としても2020年に国税による税優遇措置が明確化し、子会社であるサッカークラブへのスポンサードが広告費として損金計上することが可能となり、税制メリットを享受できるようになりました。多くのJクラブが赤字体質であり企業評価が低い、一方で、資金に余裕がある企業からすると税金として支払うよりも自社事業とのシナジー(相乗効果)があるのであればサッカークラブに投資したい。このような背景から、サッカークラブを保有したい企業へのオーナーシップの変更は近年増加傾向にあります。特にIT企業は、デジタルでのエンタメとリアルな感動体験の相乗効果を狙い、スポーツビジネスを投資領域として認識するケースが増えています。前述の国税による対処とは時代が前後しますが、2018年にFC町田ゼルビアを子会社化した株式会社サイバーエージェント、2019年に鹿島アントラーズを子会社化した株式会社メルカリ、2021年にFC東京を子会社化した株式会社MIXIなどがその代表例です。
また、特に直近の潮流として、1つの法人が異なる複数国のサッカークラブを傘下に入れて国際的なサッカークラブ運営を展開するいわゆる「マルチクラブオーナーシップ」が世界的なトレンドになっています。Jクラブが外資に買収された初の事例として、2025年よりNTTのグループ会社であった大宮アルディージャが、ドイツやオーストリア、ブラジルなどにもサッカークラブを保有するレッドブルグループの傘下となりました。

親会社からの人事異動
子会社であれば経営は親会社の意向に沿うものであり、当然に親会社を持つサッカークラブにおいてもその運営会社に対して親会社から人材派遣されるケースは多々あります。親会社から子会社であるサッカークラブへの人材派遣の種類は、以下2つに大別されます。
(1)取締役、社外取締役としての経営陣・役員の派遣
(2)実務者の派遣
前者(1)は、多くの子会社を持ちその代表取締役や役員を若手社員に任せる文化のあるIT企業を例外として除くと、多くの場合、親会社でも役員・部長クラスのおよそ40代以上の人材が派遣されるものです。一方で、後者(2)は実務者として20-30代の人材が派遣されるものであるため、本コラムのターゲットを想定し(2)についてフォーカスして説明します。
親会社への就職
子会社であるサッカークラブ側からの要望だったり、親会社側からの意向だったり様々ですが、サッカークラブの事業サイドを中心に強化したい領域があれば、親会社からの派遣をもって人員強化するケースはよく見受けられます。例えば、親会社でBtoC向けマーケティングを担ってきた人材が、サッカークラブのチケットやファンクラブ領域の強化のため派遣されたり、親会社の財務畑の人間がサッカークラブの経営管理側を統括したりする例です。
サッカークラブを保有する企業の多くはいわゆる大手企業なので、その多くが定期の新卒採用をしています。まずは親会社に新卒入社し、子会社としてのサッカークラブを管理するスポーツビジネス系部門に配属される機会を伺うのは、プロサッカークラブ運営に携わる上ではひとつの選択肢となるでしょう。新卒から大企業の整備された研修を受けられ、大企業の社員として経済規模の大きな案件にも関われる機会が豊富にあるため、そのような経験を引っ提げた状態でサッカークラブに派遣されると、自らの専門性を発揮しやすい環境で仕事ができるでしょう。一方で、当然に配属リスクは認識しなくてはなりません。大企業ですので、必ずしも自らの希望が全て叶えられるわけではありません。
サッカークラブを保有する企業のスポーツビジネス系部門に対してピンポイントでエントリーし、中途入社するパターンも選択肢となり得るでしょう。ただし、大企業のスポーツ部門においては、プロサッカークラブ運営は様々ある事業のうちのひとつである場合があります。ここでも配属リスクは認識する必要がありますが、新卒採用よりも低いものかもしれません。
さいごに
そもそも定期新卒採用をするJクラブは少ないですが、報酬の観点からもスキル開発の観点からもJクラブへの新卒入社がキャリア選択として不安であれば、Jクラブを保有する親会社を目指して就職活動をするのは選択肢としては推奨できます。サッカークラブでは機会のない種類や規模の経験や能力も身に着くでしょう。ただし、配属リスクを認識する必要はあります。自分自身の会社員時代からの経験を振り返っても、メンターや人事には自らの配属希望を伝え続けて、望むキャリアを得ることが重要になります。ただし、希望を叶えてもらうためには、たとえ望まない配属先であっても努力して結果を残し、自らの希望を公言できる環境を自分の力で整えることは大前提となります。
次回は、⑦「コンサルティングファーム」についてご紹介します。