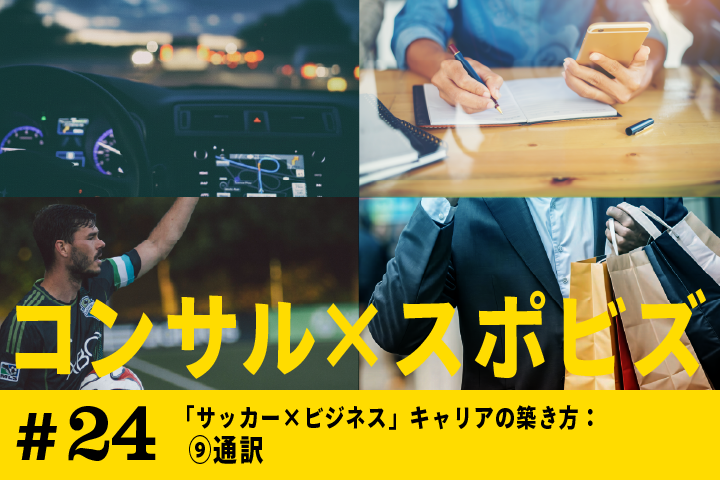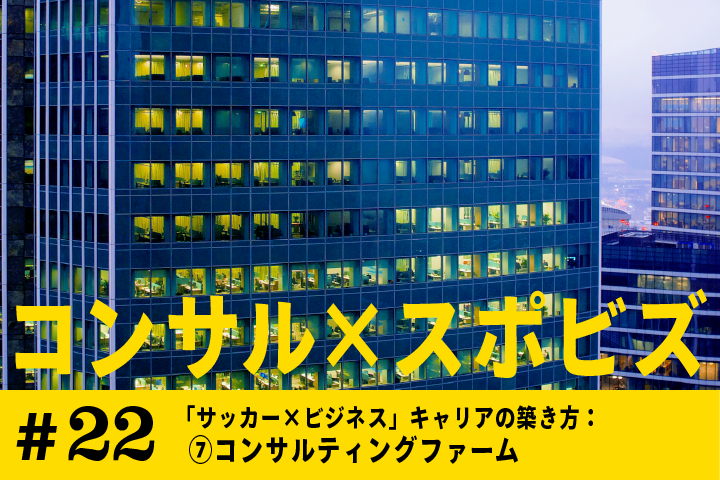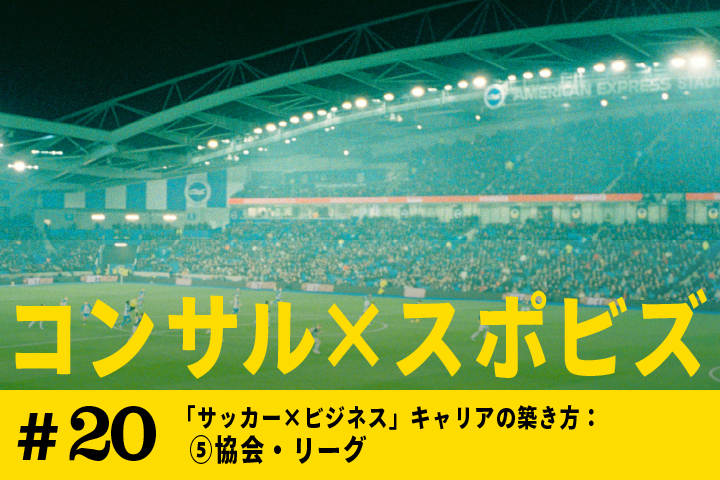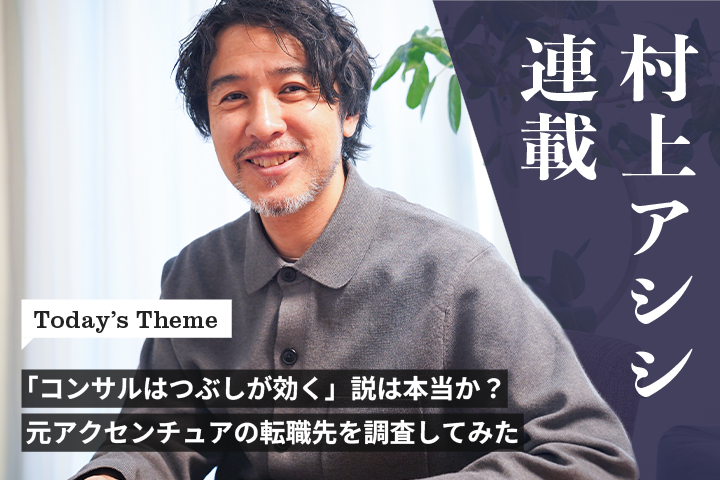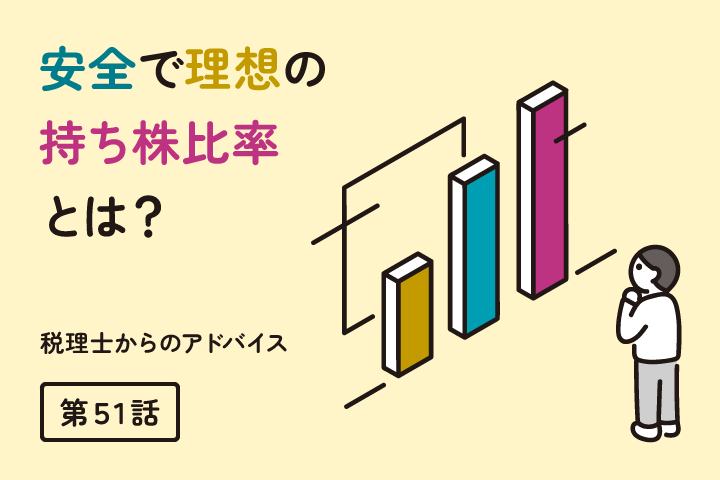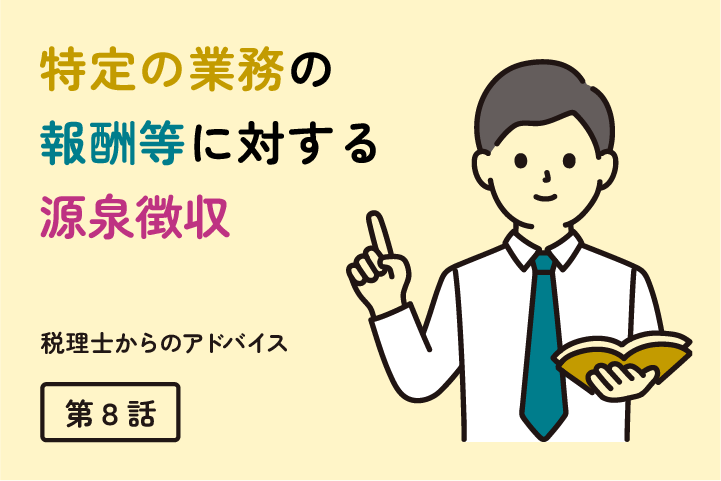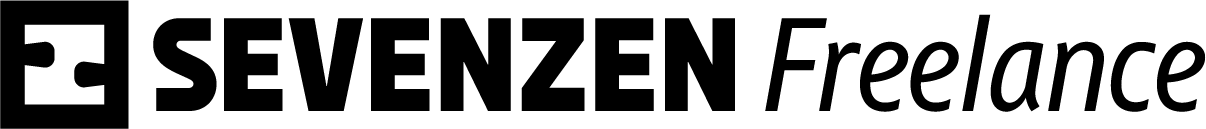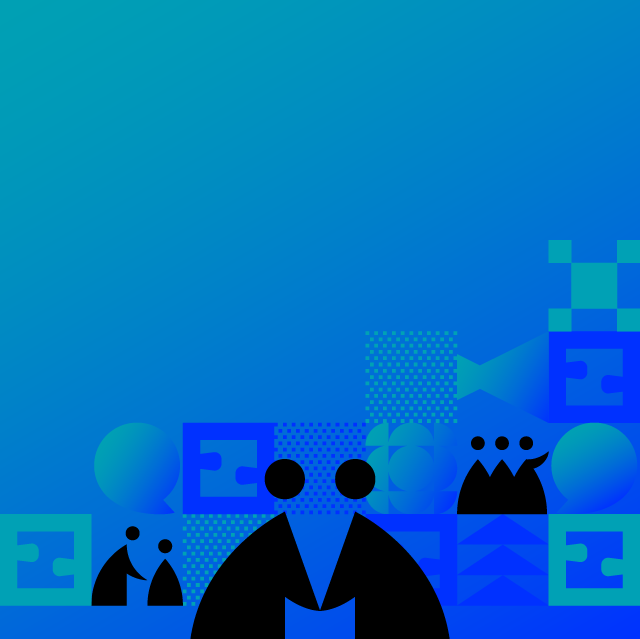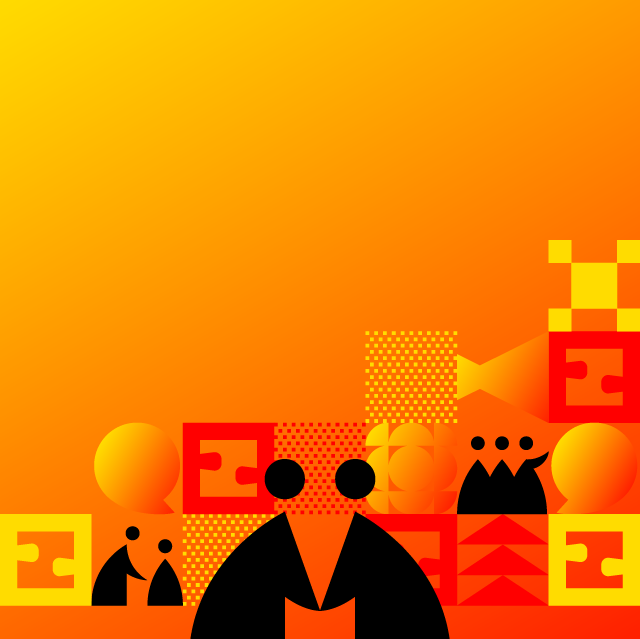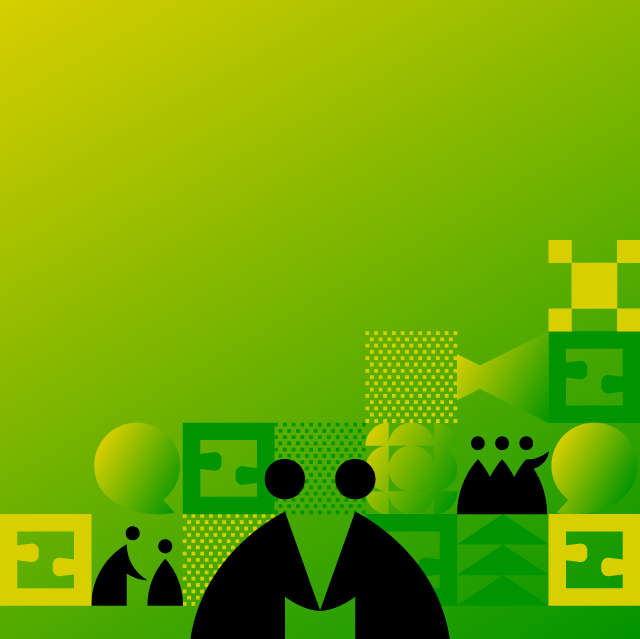「サッカー×ビジネス」キャリアの築き方、第4回目は選手を支える「サプライヤー」について、ご紹介いたします。
本題に入る前に、本連載の「前提」を振り返ります。
※本連載の全ての記事において、冒頭に「前提」を明記します。記憶が新しい方は読み飛ばしていただいて構いません。
連載の前提
■内容
「サッカー×ビジネス」というキャリアの築き方について、スポーツ部門(強化部)の周辺ステークホルダーから考えられる職種、就職の方法、得られる機会、注意点、ネクストキャリアの可能性など
■ターゲット
国内外の有名大学を卒業予定で将来はサッカー/スポーツビジネス業界でキャリアを築いていきたい学生、または、その延長にいる若手社会人
■コンセプト
単なるお仕事図鑑ではなく、スポーツ部門にいながら感じた現場のありのままの情報を届けること(情報の全体感より深さを優先)
上記を前提として、本文をご一読いただけると幸いです。
「サッカー×ビジネス」のキャリア:④サプライヤー
スポーツ業界におけるサプライヤーとは
スポーツ業界におけるサプライヤーとは、主にリーグやクラブ、大会主催者などのスポーツ団体に対して「物品提供」を行う企業を指します。物品提供は、スポーツ団体が持つ露出効果に対して直接的な金銭を支払うのではなく、その代わりに相当額の自社製品を提供するスポンサーシップの形です。業界では「VIK(Value in Kind)」と呼ばれます。
VIKで提供される品目は多岐に渡ります。例えば、アスリートが栄養補給のため口にする補食や飲料、怪我の予防のために利用するテーピングや医療器具などが代表的です。ちなみに、物品提供として現物支給をする以外にも、スポンサー企業がチームの移動や旅行手配を支援する例も多く、そのようなサービス提供によるスポーツ団体の支援をVIKに対して「VIS(Value in Service)」と呼ぶこともあります。(あまり区別せずに「VIK」と言っても意味は通じます)
本コラムでは、特にサッカークラブのスポーツ部門(強化部)と密接に関わるサプライヤーとして、チームが着用するユニフォームや練習着、選手が着用するシューズなどの「スポーツメーカー」に絞ってご説明します。
サプライヤーとサッカークラブの関わり
サプライヤーにとって、サッカークラブとの関わり方は、下記2種類に大別されます。
①チームの公式サプライヤー
②所属選手のサプライヤー
①チームの公式サプライヤーは、主にチームが公式戦で着用するユニフォームや、日々のトレーニングで着用する練習着、試合会場までの移動着などを提供します。
多くの場合、サプライヤーはチームと複数年にわたる独占契約を締結します。品目は契約内容によりますが、シャツ、ズボン、ソックスの3点セットを軸に、キャップ、ネックウォーマー、手袋、バッグなどの小物類が含まれる場合もあります。各選手のシューズ類を除き、試合や練習時に公の目に触れる主要な物品についてはサプライヤーが独占的に提供する契約をチームと締結し、チームとして提供を受ける物品に関しては、所属選手はその他メーカーの商品を身にまとわないことが基本となります。
なお、サプライヤー契約は独占契約であることが多いため、サプライヤーにとっての契約コスト(=直接的な金銭ではなく当該金額相当分の物品提供)はけっして安くありません。それでも、チームのトップパートナーとして露出及びブランディングができたり、チーム向けに制作した商品の一般販売等を通じて売上を作ったりできるメリットがあります。
②所属選手のサプライヤーは、スパイクなどのシューズ類を選手個々に提供します。
ボールを足で扱うサッカーにおいては、選手個々の足の形状や使用感によって「合う」メーカーは異なることが多いため、クラブが全選手に対して、チームサプライヤーのシューズのみを着用することを義務付けるのは簡単ではありません。そのため、チームでのサプライヤー契約にはシューズ類の独占着用は含めない傾向があります。
そのような背景から、サプライヤーから選手個々にシューズ類を提供する場合、選手個人との契約になります。したがって、基本的には両者間の調整がなされ、そこにクラブが大きく関与することはありません。ただし、前述①の通り、クラブ側は1社のメインサプライヤーと独占契約を締結することが多いため、当該契約の履行を妨げるような②の契約を選手に締結させることは回避します。そのため、選手個々のサプライヤー契約であっても、その契約書をクラブも確認し、三者間契約(選手にエージェントがいれば四者間)を締結することが一般的です。
世間一般的に想起されやすいスポーツメーカーは、世界的な大手で言えば、ナイキやアディダス、プーマなどが代表的です。また、日本の大手で言えば、アシックスやミズノなどが挙げられるでしょう。東京のサッカークラブで例示すると、2024年は東京ヴェルディは「アスレタ」、FC東京は「ニューバランス」、FC町田ゼルビアは「アディダス」がオフィシャルサプライヤーになっています。
サプライヤーと選手の関わり
選手は前述②の通り、主にシューズの提供を受ける形でサプライヤーと関わります。契約については、選手エージェントが中間に入るため、サプライヤーが選手と直接調整・交渉するケースはまれです。一方で、サプライヤー担当者と選手との関係性によっては、物品提供に関することのみならず、一般的な悩み相談や家族付き合いなど、選手個人と密な関係を築かれる方も一定数いるようです。大手サプライヤーの場合、1人の担当者が数十名を担当することもあるようで、契約選手との関わり方は会社の規模や方針、個々の選手との関係性などによって異なります。

サプライヤーへの就職
大手外資系サプライヤーを含めて、基本的には中途採用がほとんどであり、新卒求人が世に出ることはまれです。特に新卒採用を目指す場合は、大学の部活動や学連活動に庶務として参加して、業界の一般知識や業務経験、人脈などを取得・形成しておくことが重要になります。例えば、学連活動では、所属大学が参加する大会を大手サプライヤーが協賛することがあり、そのような場でサプライヤーとの接点が作られます。大学側の担当窓口として、サプライヤー担当者との会議やコミュニケーションの機会が得られ、そのような経験や人脈があることが狭き門に挑戦できる必要条件となります。
サプライヤー経由のキャリアパス
下記2つに大別されます。
①サプライヤー内でのキャリアアップ
②業界他企業への転職
①の例として、多くのサプライヤーでは、契約選手を獲得するための活動は、マーケティング系部門の担当者が担います。そのため、キャリアを積むにつれて、マーケティング領域において担当業務が幅広くなっていくパターンがあります。例えば、クライアントが、まずはサッカー選手といった「個人」単位から、徐々に、協会やリーグ、チームなど「組織」単位になったり、さらに先にはサッカー担当など「業界」単位でのマーケティングに関与したりする機会に恵まれるチャンスがあり得ます。
また、②の例としてイメージしやすいのは、選手の担当者として培った人脈を生かした転職でしょう。例えば、サッカー業界の各チームやリーグ・協会などとの関係性を築いた後に、Jリーグチームの職員や、より現場に近い職務としてマネージャーや用具係、その他にも、JリーグやWEリーグ職員、エージェント事務所への転身などがあり得ます。
その他にも、上記①を通じて専門領域におけるプロフェッショナルとしてのキャリアを培えたのであれば、当該領域で起業・独立をしたり、当該領域の専門家・管理職として全く異なる業界に転職したりするケースもあります。例えば、マーケティングを切り口として、他の消費財メーカーに転職するといったキャリアです。
おわりに
サプライヤーへの就職は、特に大手の場合、本コラムでご紹介している「サッカー×ビジネス」のキャリア選択肢の中では比較的多く、汎用的な業務スキルを獲得できる機会があるものと理解しています。例えば、スポーツ業界を起点とした一般的なメーカーとしての商品や販売、流通に関する知識、マーケティングに関する知識やスキル、契約法務に関する知見や経験などが得られるでしょう。まずはそのようなポータブルスキルを獲得しながら、将来的にサッカー業界により専門的に踏み込んでいくようなキャリアを歩みたい方にとっては、狭き門ではありますが、ファーストキャリアとしては良い選択肢になり得ると考えます。
最後に、本コラムを作成にするにあたり、東京ヴェルディでともに働かせていただいた後藤雄一さん(Xアカウント:@gtyuic)など、数名の経験者に知見をいただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。
次回は、⑤スポーツ部門及びクラブの事業環境を左右する「協会」及び「リーグ」についてご紹介します。