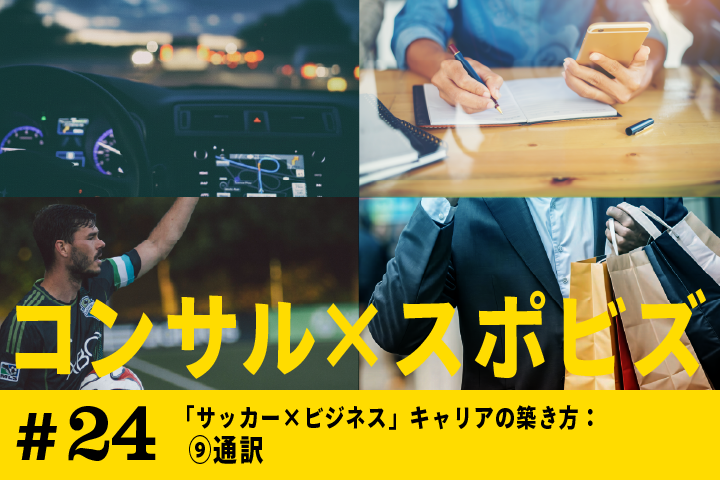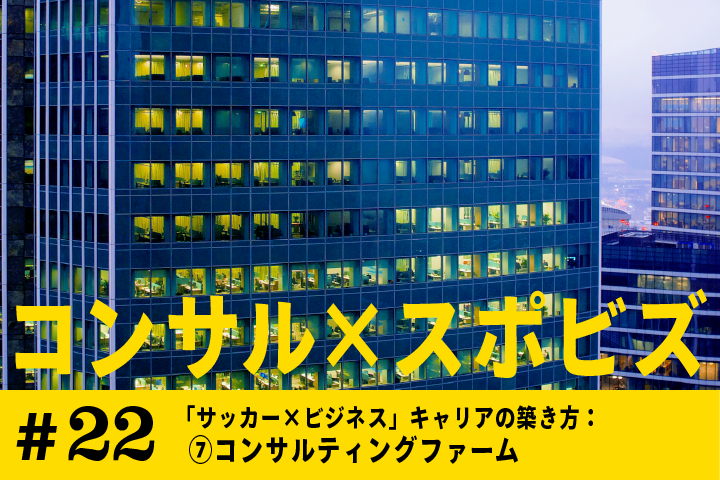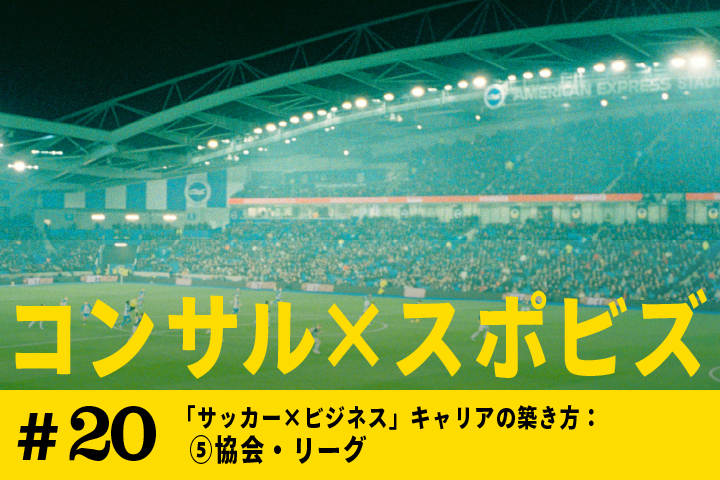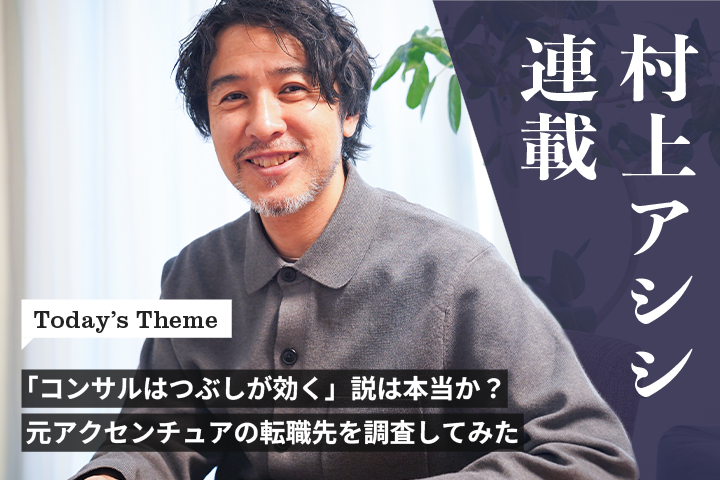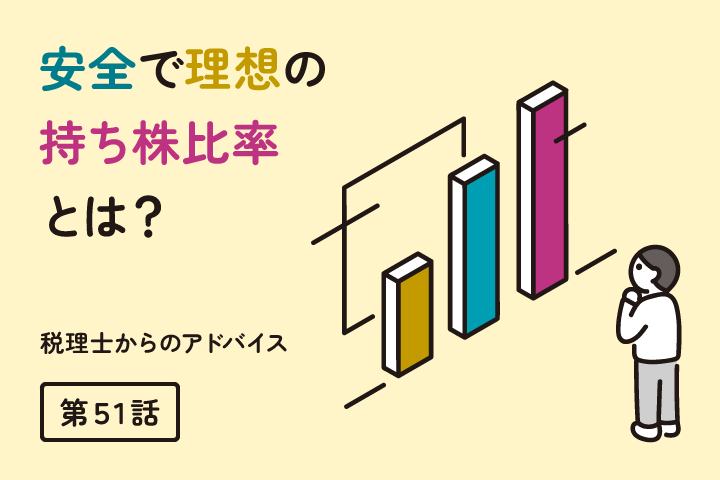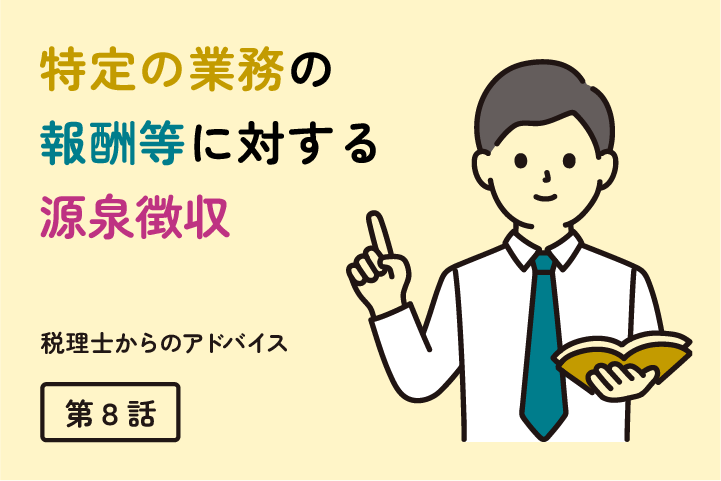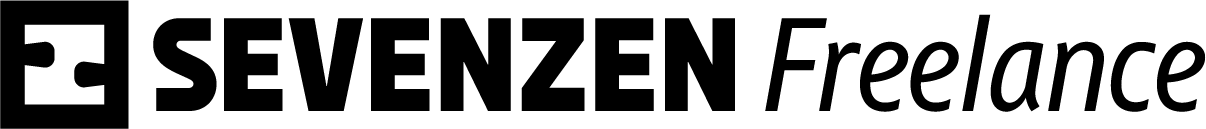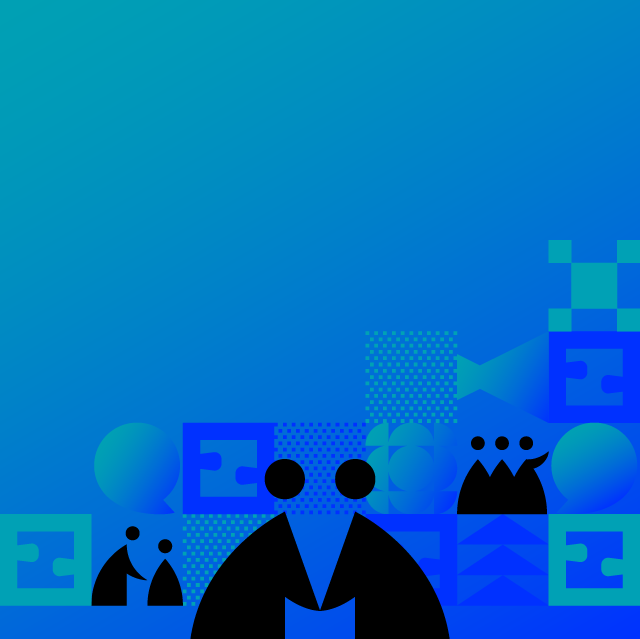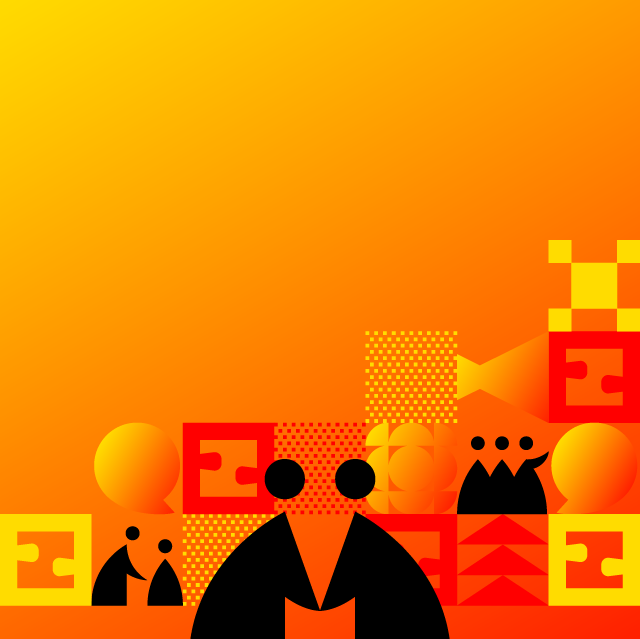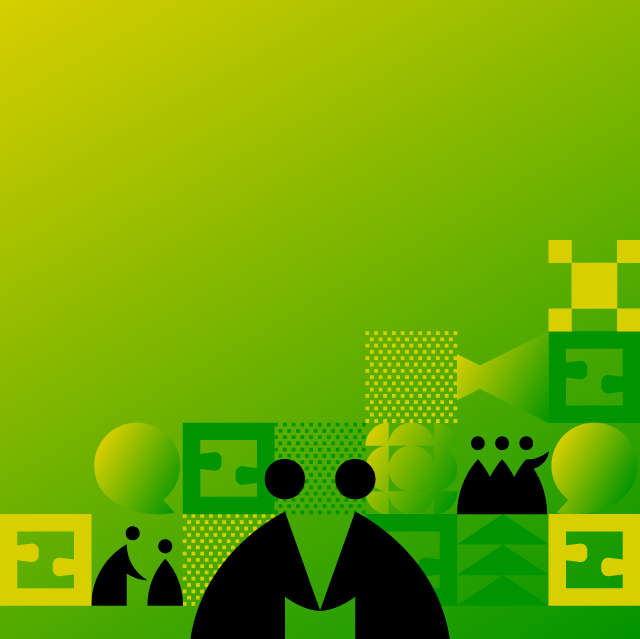コンサルファームからサッカークラブに転職してから、すでに3年目を迎えています。今や、コンサルファームで働いていた頃が、すでに遠い過去のように感じます。それほどサッカークラブで働く現在のワークスタイルに馴染んできたと言えるのかもしれません。
前回の記事でもご紹介した通り、自分自身の雇用形態が正社員から業務委託に変わったこと、または、勤務先が従業員数3,000人ほどの巨大組織から100人に満たない少人数の組織に変わったこと・・・理由は様々考えられますが、ワークスタイルにも少なくない変化がありました。
働き方の変化
ここ2-3年で「リモートワーク」という言葉が市民権を得た印象ですが、私個人にとっては、コンサルファーム時代から変わらず「縁遠い」ワードです。私がコンサルファームを退社したのは、新型コロナウイルスなるものが中国武漢で確認されるも、日本にとってはまだ対岸の火事だった頃。プロジェクトメンバーとのコミュニケーションの容易性を考慮しても、リモートワークは主流ではありませんでした。深夜まで会議室にこもっては、ホワイトボードにああでもないこうでもないと議論を書き下す風景が、コンサルファームから失われている世界を未だ想像できません。今働いているサッカークラブにおいても、サッカーという競技は当然teamsやzoom上ではできませんので、選手・スタッフは常にクラブハウスで働く中で、私もチームにアクシデントが起きたらすぐに対応できるよう基本的には出勤しています。「基本的にはオフィスで働く」というワークスタイルは、数少ない「変わらなかったこと」でしょう。
一方で、働く時間や繁忙期の波については180°変わりました。
コンサルは、プロジェクト特性にもよりますが、オンオフの波が極めて明確です。オンの時期、すなわちプロジェクト関与中は、それこそ毎日が終電で帰れるかどうかの瀬戸際。23時頃または日付が変わるまで働きつめて、間に合えば終電・逃せばタクシーで帰るといった働き方をプロジェクト期間中の数ヶ月間継続します。一方で、オフのタイミング、例えば、週次のクライアントミーティングが終われば、まだ夕方だろうと帰宅したり、プロジェクトが終われば、次のプロジェクトにアサインされるまで1週間程度連続した休みを取ったりしていました。「コンサルには土日休みがない」という噂は都市伝説であり、平日は猛烈に働き、土日祝は猛烈にリフレッシュするというワークスタイルでした。夏休みや年末年始の休暇も、プロジェクトの状況次第では、9日以上取得することが多々ありました。
サッカークラブに来てからは、オンオフの境界線を感じなくなりました。前回記事の通り、事業部と強化部とでは働き方が異なることを前提に、強化部に入ってから、オフは基本的に週1日・連戦の週はなし。アウェイゲームの日は自宅で試合を見ています。サッカーの試合を見ることが、コンサル時代は「趣味」でしたが、今は「仕事」とも言え、まずこの境目がなくなりました。他にも、コンサル時代のように毎日深夜まで働きつめることはなくなりましたが、一方で、オフの日が世間や事業部ともずれるからこそ、電話やメール、Slack、LINE、Whatsappのいずれかが常にオンです。自宅でオフを過ごしながら、電話やメールが来ればその瞬間だけオンになり、メッセージを返したらまたオフに戻る。そんな生活を送っています。
加えて、選手やスタッフは、シーズンが終われば翌シーズンが始まるまで長期休暇を取得できますが、強化部はそこからが一年の最繁忙期。選手・スタッフの契約更新や移籍加入・退団の佳境を1ヶ月ほど過ごし、そのまま年末年始を終えると、休む間もなく新たな体制でのシーズンを迎えます。9日以上の休暇が夏と冬に2回あったコンサル時代とは異なり、サッカークラブに来てからは3日以上連続する休みを取ることは難しいと割り切っています。その反面、コンサル時代のような「寿命をすり減らす」働き方はしなくなりました。
どちらの働き方もメリット・デメリットがあるので、どちらが良い・悪いという話ではありませんが、やはり働く環境を変えたらワークスタイルも変わるのが常であるため、「適応力」は重要だと改めて感じています。

業務上の価値観の変化
業務に対する意識の変化も少なからずあります。簡単な例だと、業務上の日々のプレッシャーをどこに感じるか、という点は変わったように思えます。
コンサル時代は、端的に「プレッシャー=緊張感」のニュアンスを強く持っていました。日々の業務においては常に先輩や上司に評価される緊張感。常駐先やクライアントミーティングにおいては常にクライアントから能力を推し量られている緊張感。また、都心の高層オフィスにスーツをバシッと着て入り、巨大なミーティングルームで大企業の役員たちとのミーティング臨む、そのようなシチュエーションへの緊張感もありました。
一方で、おそらく大企業からベンチャー企業に転職した方の多くは同じような印象を持つのかもしれませんが、少人数組織であるサッカークラブにいる現在は、「プレッシャー=責任感」のニュアンスが強くなっています。当然、会社経営陣の最終承認や顧問弁護士への相談といった防波堤はありつつも、部門予算の執行、契約のスキーム検討や締結など、自分が強化部におけるビジネス面の実行責任者であることへの重圧は日々感じています。コンサル時代は、自分と同種のスキルを持つ人間が社内に多くいたので、究極的には自分が倒れても社内の調整で何とかなるものです。サッカークラブ、こと強化部に来てからは、自分がコンサル時代に培ったスキルを持つ人間は限られるため、自分がやらねばという責任感としてのプレッシャーが、対クライアントではなく、会社に対して強くなったように感じます。
その他の小さな変化
細かい変化で言えば、コスト意識は大きく変わりました。前述の通り、コンサル時代は終電を逃せばとりあえずタクシーで帰り、数千から数万円のコストがどれほど積み上がろうと気に留めていませんでした。コンサルファームにおけるプロジェクト経費の考え方は、クライアントからいただくフィーの数パーセントを経費にする、というもの。そのため、ひとつのプロジェクトでも、数十万円から多ければ数百万円の余裕があります。「経費をいくらかけてでも良いものを作る」という文化であったため、無駄な経費をいかに抑えるかという議論はおざなりになっていたように感じます。一般的には、けっして常識的とは言えない考え方でしょう。(今では、コンサルファームもプロジェクト経費への感度が変わっているかもしれません)
他方、サッカークラブはいち中小企業であり、数百円であってもいかにコストを抑えるかを真剣に考えます。自分がコストを使う側から管理する側になったのが一番の理由だとは思いますが、コスト意識について「そうあるべき姿」になれたのは、転職して良かったことのひとつでしょう。
その他、コロナ禍だからなのか、通勤手段が電車から車に変わったからなのか、または、勤務地が東京23区から外れたからなのか、いずれにせよ、会食の機会は激減しました。コンサル時代には、社内打ち上げやクライアントとの会食用に飲食店リストをストックして良いお店を確保することも、自分自身の価値を高める重要な業務でした。だからこそ、毎回結構な配慮をしていましたが、その心配がなくなったのは気が楽です。
電車とタクシーにもほとんど乗らなくなりました。業務でタクシーを利用するのは、サッカークラブにとっては少なくないコストがかかるため、基本的には選択肢としてなし。今では電車に乗ることすら億劫になりました。練習場やスタジアムは、広大な土地が必要であることから、大抵は駅から離れた場所にあり、車移動が便利です。自分も転職を機に車を購入し、車移動が中心になりました。ペーパードライバーを卒業できたのも、サッカークラブに転職して良かったことのひとつかもしれません。
大小いろいろな変化がありますが、転職によって価値観が異なる環境に身を置き、自分自身の考え方をアップデートしていく作業の面白さは日々実感しています。