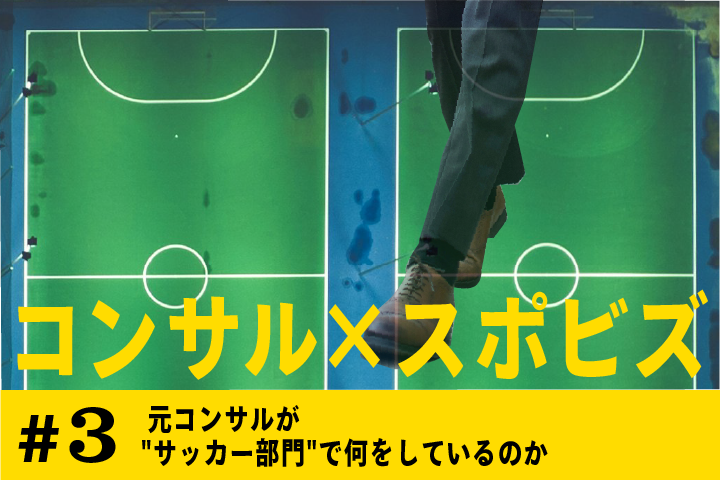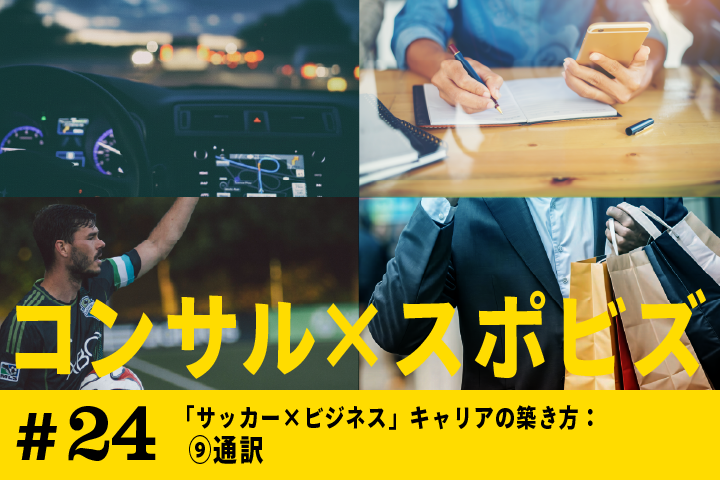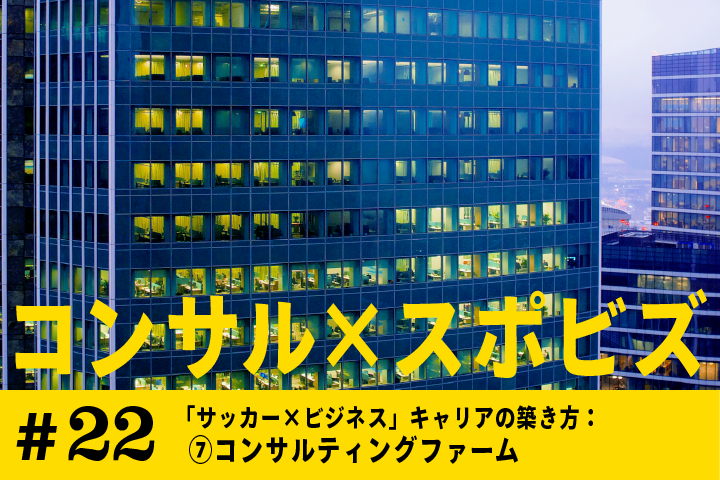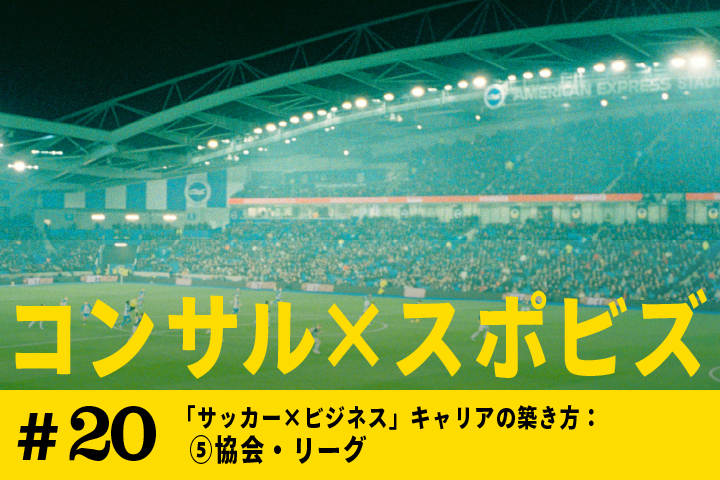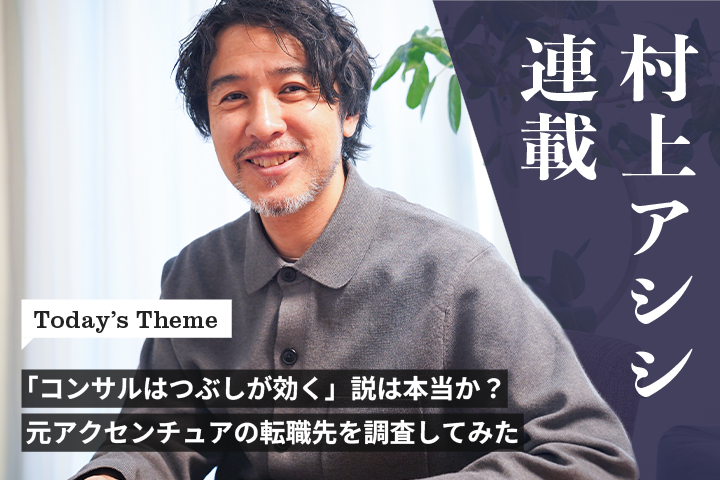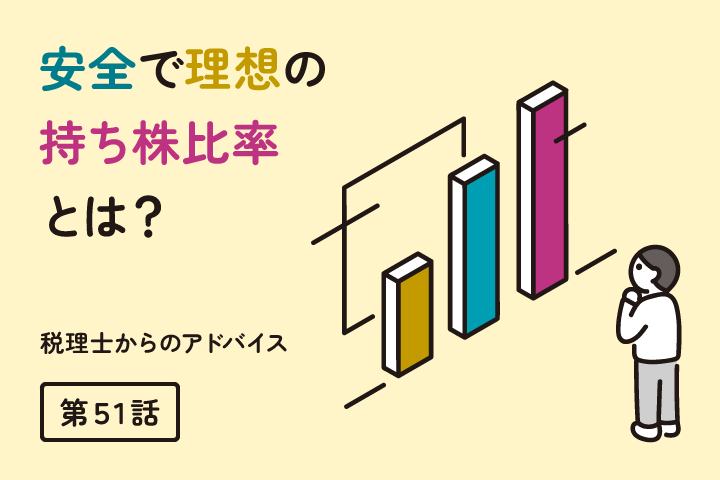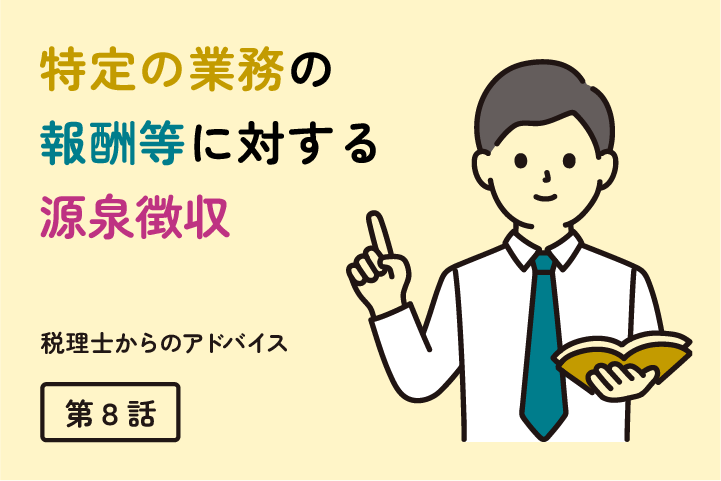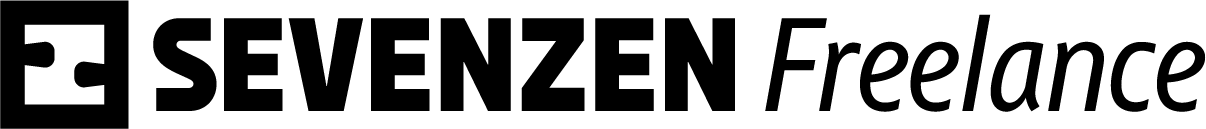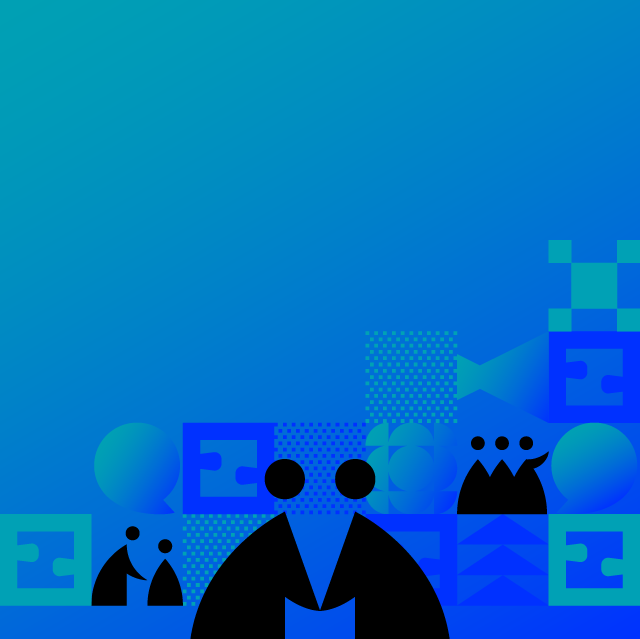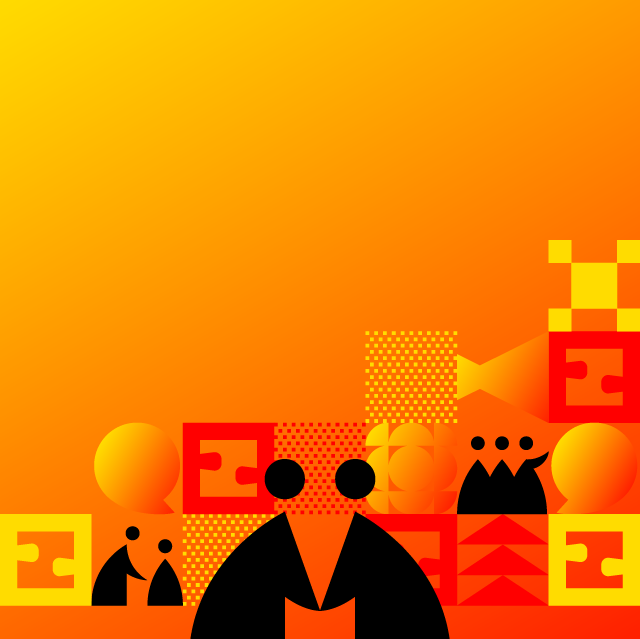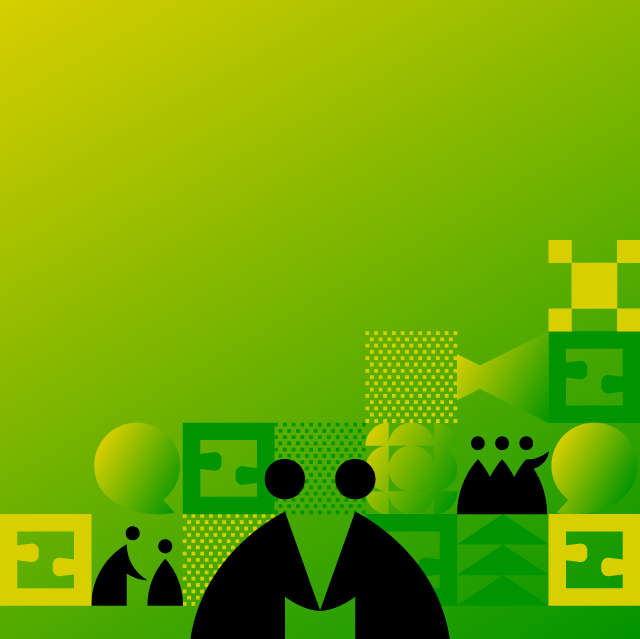コラム#1では、サッカー部門(=強化部)とは「プロサッカーチームの編成・マネジメントを担当する部門である」ことを触り程度にご説明しました。今回は、元経営コンサルタントの私がサッカー部門でどのような仕事をしているのか、より具体的にご紹介したいと思います。
主な業務内容はコンサル時代とほぼ同じ
元プロサッカー選手でもなければ、プロの監督・コーチ、分析官としての経験もない私が、プロ選手のスカウトやプロチームのパフォーマンス分析を担当することはありません。私はその裏側、つまり、部門の業務をビジネスとして効率良く、かつ、付加価値高く運用する業務に対して責任を負っています。
実は、私がサッカー部門で担当している多くの業務は、コンサル時代と大きく変わりません。つまり、部門戦略・実行計画の立案、業務改善、プロジェクトマネジメントなど、上流から中流までのコンサルティング業務をそのままサッカー部門でも取り組んでいる\ようなイメージです。大きく変わったのは、自らの立ち位置がコンサルタントから組織内の実務責任者になったことでしょう。
参考として、東京ヴェルディに来てから約2年間の中で取り組んできた/現在も取り組んでいる業務を下記にいくつか列挙します。
■部門戦略・実行計画の立案
・全社ミッションに紐付く強化部ミッションの定義
・ミッション達成のための、5-10年先を見据えた中長期ビジョンの定義
・ビジョン達成のための、直近3年間のアクションプランの立案
競技としてのサッカーの専門領域を含む戦略・計画立案であるため、強化部メンバー全員の意見を集約しながら明文化しました。
■業務プロセスの改善、標準化
・部門予算の立案・進捗管理の仕組み設計
・選手及びスタッフの契約状況デジタル一元管理
・選手及びスタッフの想定される成績に応じた変動ボーナスシミュレーションの仕組み設計
・選手契約・登録業務の標準化(契約パターンごとの対応事項・必要書類等の整理と可視化)
・契約パターンごとの契約書標準化
・外部スカウティングシステムを活用したデータスカウティングの仕組み構築
特に属人化しがちな予算管理・契約業務については、年間を通じて全て自ら手がけ、同時進行で、クラブの資産として未来永劫残る標準化された仕組みへと構造化していきました。
今後別コラムで詳述しますが、選手契約に係る費用、及び、選手の契約・登録業務には、どちらも多岐に渡る種類があり、そのルールは日本サッカー協会のガイドラインによって厳格に定められています。全てのパターンを網羅した上で、それぞれを管理システムとして可視化することで、より精度の高い予算計画が可能となり、かつ、契約・登録業務の生産性も向上しました。
ちなみに、上記は主要業務の一例であり、ここには書き切れない小規模な業務改善についても、都度実行しています。
■プロジェクトの管理、遂行
・各種強化部プロジェクトのPMO
・新規プロジェクトの企画・リード
強化部では、トップチームの編成に加えて、組織設計や仕組みづくりが中心的な業務となります。その中で、部門の他スタッフが抱える案件をプロジェクトマネジメントの側面から支援したり、自らも新規案件を企画・実行のリードをしたりしています。
入社初年度に強化部業務のいわば土台となる予算管理や契約・登録業務の仕組み設計がひと段落したため、最近の関心事は組織・チームとしての付加価値をより高めていく領域に移っています。具体的には、選手教育の仕組みやHRM(ヒューマンリソースマネジメント)システムの設計などについて、検討・実行を深め始めた段階です。その他にも、男子チームで1年間かけて取り入れた上記の仕組みを、女子チームにも少しずつ展開していく作業にも2年目から取り組んでいます。

一方でコンサル時代とは異なる業務も
上記のようないわゆるコンサル的業務を実務責任者としてこなしつつ、同時に、コンサル時代にはあまり経験してこなかった新たな業務にも挑戦させてもらっています。その最たる例が、毎シーズンの「チーム編成」です。
具体的には、選手代理人との協議、契約内容の検討、契約書の作成、選手登録業務の統括などを担当しています。東京ヴェルディの強化部に来てから今年で3年目になりますが、クラブ内の組織変更に伴って私自身の担当領域も年々拡大する中、毎年アップデートしながら挑戦することができています。
例年、年末年始はこの編成業務に追われ、強化部にとっては1年間の最繁忙期を迎えます。その中で、プロ選手やプロコーチとして経験豊富な「競技としてのサッカーの専門家」である強化部長が目指すビジョンやチームを実現すべく、私は「ビジネスとしてのサッカーの専門家」として二人三脚で編成業務を邁進しています。
具体的な役割分担としては、中長期的なビジョンの達成に向けて、前シーズンのチームが抱えていた課題を解決するために、強化部長がチーム全体の戦い方やチーム編成をイメージしながら、新たに迎え入れたい選手の代理人に声をかけていきます。私は主に、強化部長がファーストコンタクトを済ませた代理人と契約内容を協議する以降のプロセスを預かります。その際に、契約年数や報酬金額などの契約内容は、強化部長や場合によっては経営陣とも相談・合意形成しながら、会社に与えられた全体の編成予算枠に収まる範囲内で調整していきます。そして、代理人と合意に至った後は、契約書類の作成に取り掛かります。
上記に例示した役割分担は新規加入の選手についてですが、前年から引き続きチームに所属していただく選手については、シーズン末に経営陣・強化部長とともに選手に対して翌シーズンの条件提示をした上で、シーズン終了後に私から代理人の皆さんにコンタクトを取り、翌シーズンの契約内容に関する協議を進めていきます。
このように、選手編成の実務は基本的に強化部長と2人で進めていますが、様々な方々のサポートは欠かせません。例えば、具体的な選手編成はチームの指揮を執る監督やコーチングスタッフの意向も踏まえながら決定します。また、選手やスタッフの入れ替わりがある場合は、代理人の皆さんからのご紹介や、チームの他スタッフからの紹介にも存分に頼らせてもらいます(例:クラブドクターの繋がりの中でメディカルスタッフをご紹介いただくなど)。そして、選手及びスタッフの加入または継続をリリースする作業は広報が進めてくれます。その他、大学生選手などについては、シーズン中にスカウト担当者が視察や強化部長への共有を行い、強化部長の最終判断のもと年末年始の編成業務以前に内定を決める新人選手のスカウティング業務も発生します。つまり、チームの編成業務は、強化部の範囲を越えたクラブ全体、さらには、代理人の皆さんを始めとする外部の方々のサポートもあって成り立つものであることは、誤解なきようここに明記しておきます。
そうは言いつつも、新規加入もしくは継続選手を30名以上、スタッフを15名以上、合計50名近いチームメンバーとの個別契約を、1ヶ月にも満たないごくわずかな期間で取りまとめなくてはならないのも事実。ここでコンサル時代に培った能力や経験が活かされていることは、年々実感を深めています。
競技としてのサッカーの専門家でなくともサッカー部門で価値を発揮できる
私には、プロ選手のスカウティングやプロチームのパフォーマンス分析はできません。なぜなら、競技としてのプロサッカーに関する資格も経験もなく、サッカー部門というまさに競技としてのプロサッカーの中心とも言える世界で私がそのようなことをしたところで、まるで説得力がないからです。一方で、上記のようなビジネスの視点からサッカー部門を運営することはできます。そのための資格も経験も説得力もあると自負しています。
ここまでご紹介したように、元経営コンサルタントだからこそ価値を発揮できる業務が、実はサッカー部門にはいくつもあります。サッカー部門、ひいては、あらゆる競技のスポーツ部門においても、ビジネス的な業務をより効率的かつ付加価値高く実行したいという需要が増えること、また、それに応じてスポーツ部門というスポーツビジネスのまさにど真ん中の領域において、ビジネスのバックグラウンドを持つ人材が力を発揮できる機会が増えることを切に願っています。本コラムがそのような未来に少しでも近づくきっかけになれば本望です。