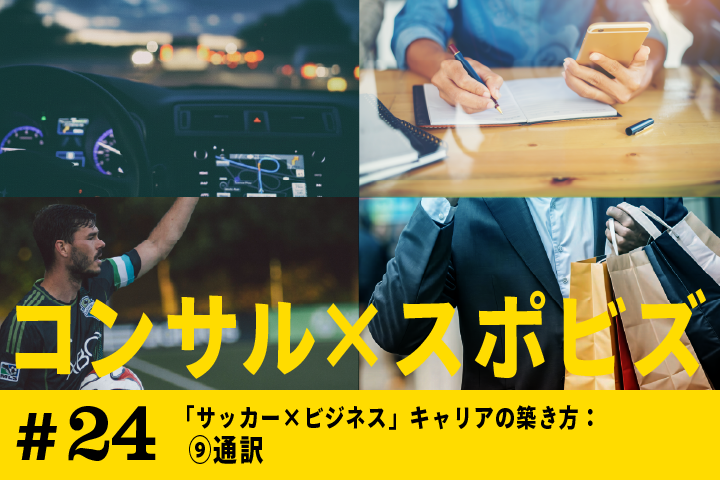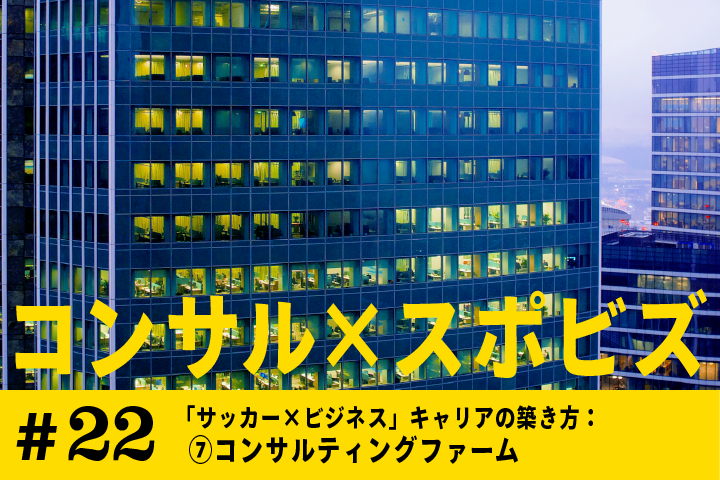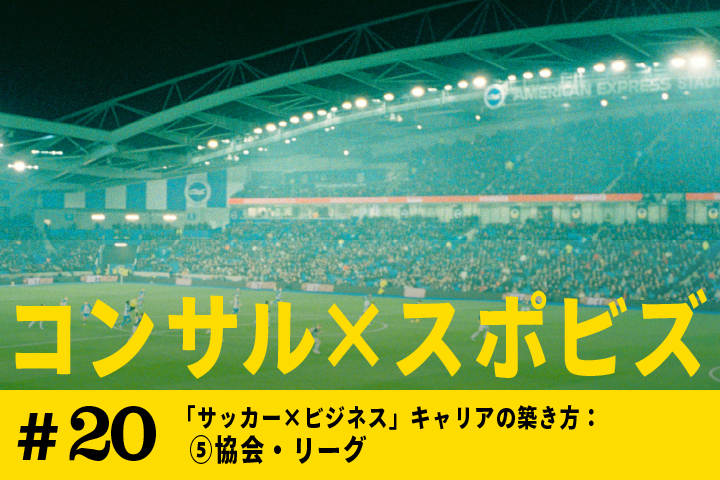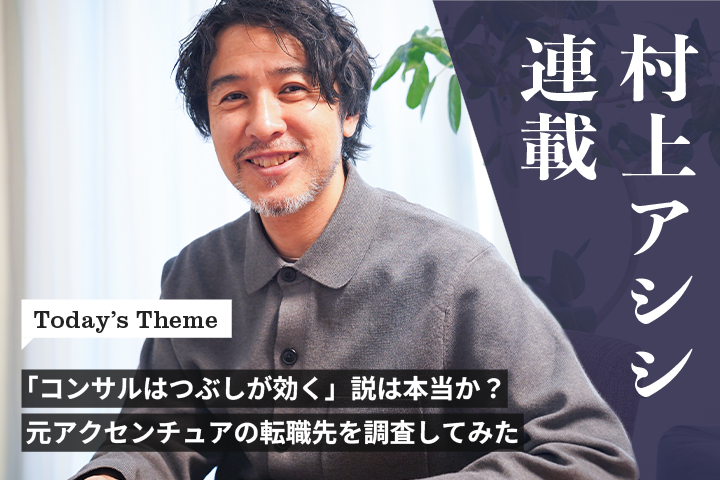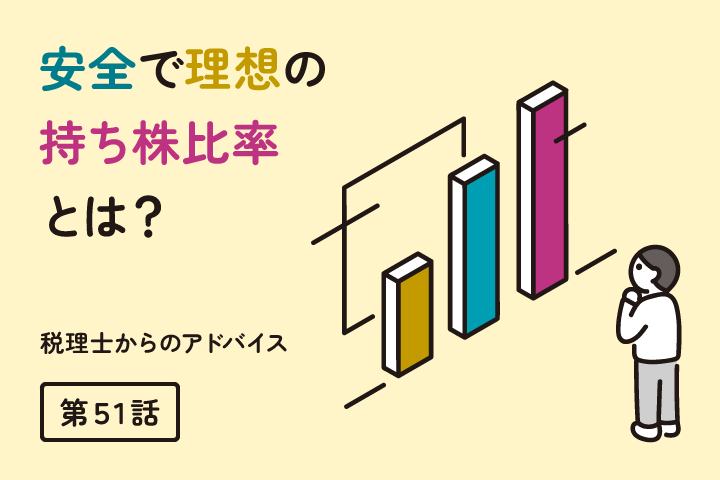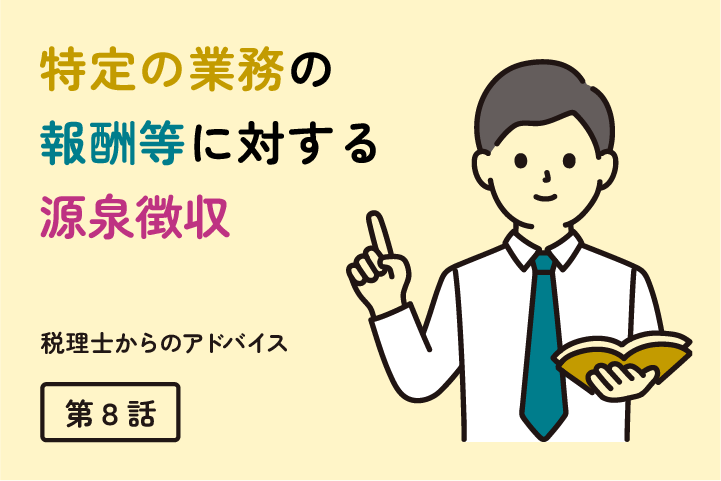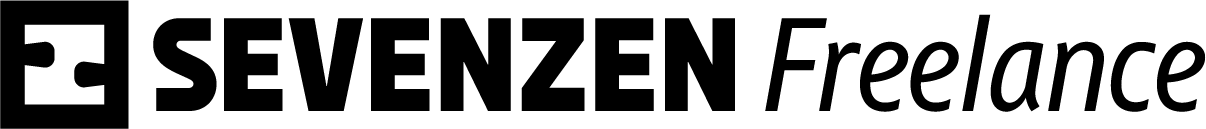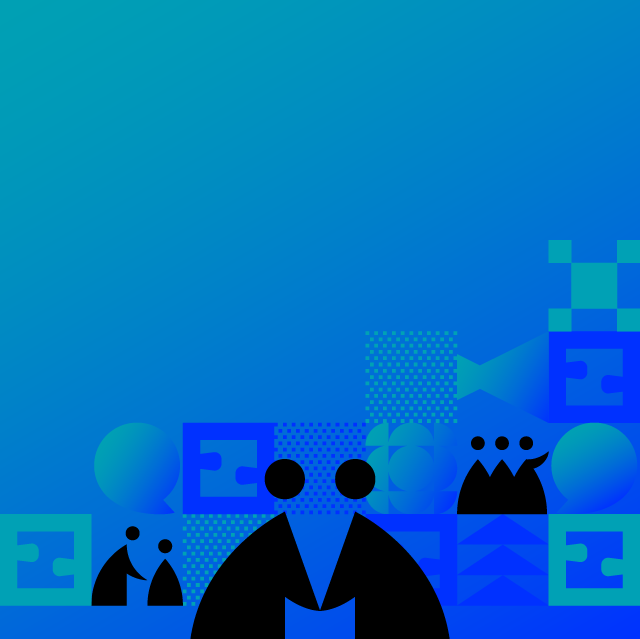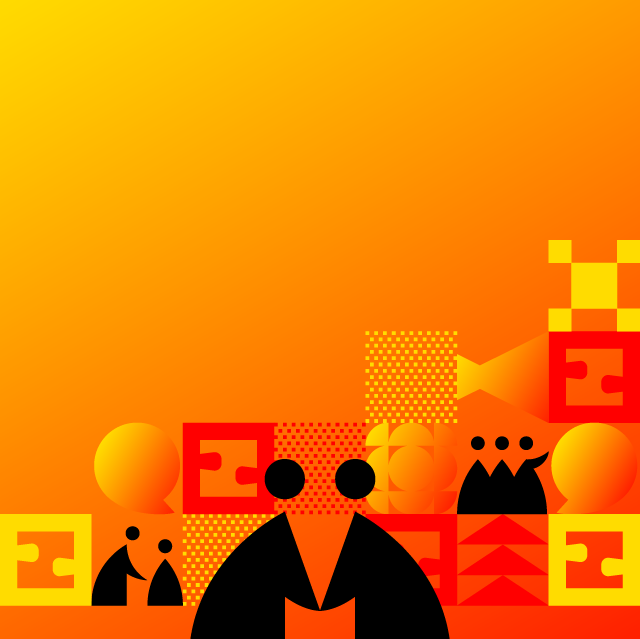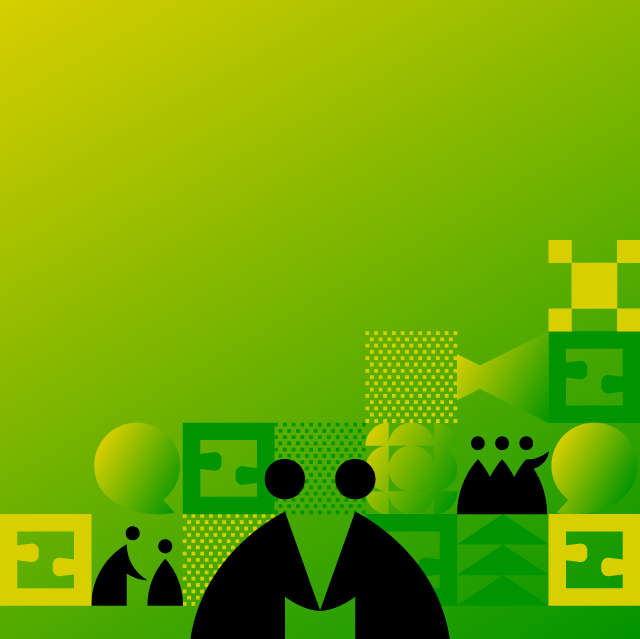「サッカー×ビジネス」キャリアの築き方の連載において、第1-6回目までは、サッカービジネスのど真ん中に位置する「スポーツ部門(強化部)」とそれに直接的な影響を与え得る周辺産業におけるキャリアについて解説しました。
第7回からは3回に分けて、自分自身のこれまでのキャリア(大学の外国語学部⇒コンサルティングファーム⇒個人事業主として独立・プロサッカークラブと契約)を踏まえ、特に読者の皆様に経験則をお届けしたい「コンサルティングファーム」「フリーランス/個人事業主」「通訳」というキャリアについてご紹介いたします。
(私のこれまでのキャリアについては、こちらの記事でもお話しています。)
第9回目は「通訳」について、ご紹介いたします。
本題に入る前に、本連載の「前提」を振り返ります。
※本連載の全ての記事において、冒頭に「前提」を明記します。記憶が新しい方は読み飛ばしていただいて構いません。
連載の前提
■内容
「サッカー×ビジネス」というキャリアの築き方について、スポーツ部門(強化部)の周辺ステークホルダーから考えられる職種、就職の方法、得られる機会、注意点、ネクストキャリアの可能性など
■ターゲット
国内外の有名大学を卒業予定で将来はサッカー/スポーツビジネス業界でキャリアを築いていきたい学生、または、その延長にいる若手社会人
■コンセプト
単なるお仕事図鑑ではなく、スポーツ部門にいながら感じた現場のありのままの情報を届けること(情報の全体感より深さを優先)
上記を前提として、本文をご一読いただけると幸いです。
「サッカー×ビジネス」のキャリア:⑨ 通訳
サッカークラブにおける通訳の仕事
まず前提として、サッカークラブにおける「通訳」とは、主に2つの役職に分かれます。それは「監督通訳」と「選手通訳」です。ただし、後者の方が、Jクラブにおいては業務機会が圧倒的に多く、また、自分自身も過去の経験を踏まえてお伝えできることが多いため、本稿は「通訳」=「選手通訳」という前提で進めます。
さて、通訳業務は、大きく分けて2つに分類することができます。それは「オンザピッチ」業務と「オフザピッチ」業務です。前者がピッチ内、つまりサッカーという競技に関する通訳業務、後者がピッチ外、つまり日常生活に関する通訳業務です。
一般的に選手通訳という職業を聞いて頭に思い浮かべられるのは、試合で大活躍した選手が中継のインタビューに答え、そのすぐ隣で通訳をしている姿でしょう。このような、いわゆる「花形的な」通訳業務が「オンザピッチ」の通訳です。他にも、日々の練習やミーティングで選手に付き添い、監督やスタッフ、チームメイトとのコミュニケーションを円滑に仲介する業務。もしくは、試合中に監督が選手を呼び止めた際にその指示を通訳する、または、選手がプレー中に身体を痛めた場合にメディカルスタッフとともにピッチ内にかけつけ状態を確認するといったシーンもよく思い浮かぶでしょう。
一方で、このようなスポットライトが当たる華やかな業務の裏側には、それ以上に多く、光の当たらない泥臭い業務があります。それが「オフザピッチ」の通訳です。いわゆる日常生活の支援です。クラブ(強化部/スポーツ部門)が外国籍選手との契約を決定し、チームにその情報が下りたら、その直後にオフザピッチの通訳業務が始まります。
来日までにクラブやチームから伝達すべきこと(例えば、住居の情報やコンディション維持のためのトレーニング内容、など)を共有する。
来日当日は空港まで迎えに行き、クラブが手配した住居やホテルまで送迎する。
(※クラブによっては、住居手配も通訳業務の一環としている場合もあります)
来日後に落ち着いたら市役所まで行き住民登録を行う。
日本の生活に慣れるまでは、あらゆる買い物や食事に付き添う。
国内の銀行口座の開設や携帯電話(simカード)の契約に付き添う。
試合や練習で怪我をすれば、完治するまでMRIや治療など通院に何度も付き添う。
日本の運転免許を取得するまでは、上記の付き添いに関する送迎を全て行う。運転免許の取得に際しては免許センターまで付き添う。
緊急で困りごとが発生すれば、WhatsAppで相談に乗ってあげたり、必要であればすぐにかけつけたりする。
当該選手の家族が来日を望めば、家族分についても上記同様のお世話をする。
在籍中に結婚や出産、子どもの保育園入園や学校入学といったライフイベントがあれば、その事務手続きを全てサポートする。
このような、人によっては雑務と捉えられかねない細やかな仕事も、立派な通訳業務の一環なのです。通訳を志すのであれば、華やかなオンザピッチ業務よりも泥臭いオフザピッチ業務の方が、実は割合として多いことをまず認識することが重要です。
私自身、過去の記事でご紹介した通り、強化部スタッフとして求められた背景のひとつが、ブラジル人選手のお世話係でした。当時、ブラジル人選手のオンザピッチ通訳がコーチ兼務ということもあり、オフザピッチの世話をする余裕がなく、彼らの日常生活へのサポートが不足していました。強化部所属1年目は、3名のブラジル人選手の日常サポートに多くの時間をかけたことを今でも思い出します。
例えば、私ともう一人の外国語を話せる強化担当と交代交代で自宅⇔練習場の送迎を毎朝毎晩欠かさず行ったり、時には通院のために当時ペーパードライバーながら人生で初めて首都高に乗り、ド緊張しながら茨城県にある病院まで付き添ったり。または、チームと強化部の休日は重なることが多いですが、選手は休日こそ買い物などの要望があるため、休日返上で選手をサポートしたり。はたまた、自宅で音楽を大音量で聞いていた選手に周辺住民から警察に対して苦情が入り、突然警察が家を訪ねてきたので選手が焦って私に通話をかけてきて、夜中に突然電話口で警察に事情を説明し謝罪をすることになったり。特に、当時はコロナ禍真っただ中だったので、家族が来日することもままならず、選手もストレスを抱えることが多く、サポートが大変だった記憶が鮮明に蘇ります。
通訳として持つべき心構え
再掲になりますが、練習や試合だけで通訳をしていれば業務が完結するわけではありません。特に、選手が急に体調を崩した場合は、夜間だろうと休日だろうと自らの予定より優先しなくてはならないシーンも出てきます。このような状況を否定的に捉えない姿勢が大前提です。
サッカーという興行における主役はあくまで選手であり、通訳はいわゆる黒子的な存在です。選手の成功とチームの勝利に尽くすんだという心構えが最重要です。そのような姿勢が伝わると、選手も一人の人間なので感謝をしてくれます。良し悪しではなく性格や志向として、「ワークライフバランスを重視したい」「何よりも自分の生活を大切にしたい」といった人生観を持っている方には、通訳という仕事は向きません。
一方で、相反することを言うようですが、選手に寄り添い過ぎてもいけません。この絶妙な距離感が通訳という職業の難しいところです。通訳はあくまで「クラブの人間」です。なぜなら、通訳に報酬を支払っているのは選手ではなくクラブだから。選手に24時間365日付き添うからと言って、単なる選手の「友達」であってはいけません。クラブは選手を管理する側なので、「通訳=クラブの人間」なのであれば、通訳にもクラブの意向を踏まえながら選手とうまく付き合わなくてはならないシーンが発生します。たとえそれが選手の要望とは正反対であっても、何とか理解・納得させるようなコミュニケーションが必要になるのです。
通訳が100%選手側につくようであれば、通訳の報酬は選手が支払えばよいとクラブの人間は率直に思うでしょう。通訳とは、クラブに雇われその意向に沿いながらも、同時に選手のパフォーマンスが最大化するようにサポートする働き方が求められる簡単ではないポジションです。時にクラブと選手の間に挟まれる中で、両者を取り持つバランス感覚や、選手をある種マネジメントしながら、モチベーション高く練習や試合に集中してもらうような動機付けやコミュニケーションを発揮すること。通訳業務というのは、実は「マネジメント」の要素が大きいのです。単なる言語が上手な選手の友達やお世話係では、クラブからの期待としては不十分です。それでは「狭義」の通訳でしかありません。選手やクラブの人間をマネジメントできる「広義」の通訳として振る舞える方こそが、選手とクラブの両方から評判が良く、業界内でも信頼されて長くご活躍されている印象です。
通訳になる上での注意点
冒頭に記載した通り、本稿のターゲットは有名大学出身でスポーツやサッカーに関わりたい方々です。私自身も外国語学部卒なので、母校もしくは似たような学部の学生、または海外留学経験のある大学生から相談を受ける機会が多くありました。
その際に、彼らに必ず質問するようにしていたのは、上記のような泥臭い業務が多々あることを共有し、職も不安定であることを正直に伝えた上で、それでもなお通訳を志すのかという覚悟です。「大学で語学を勉強したため、それを活かせる仕事に就きたい。それが好きなサッカーであればベスト」というだけの願望であれば、むしろサッカークラブの通訳にはならない方がよいと断言できます(特に、新卒カードを切るのであればなおさら)。
チームスタッフは多くが社員ではなく業務委託契約であるため、そもそも該当する外国籍選手がチームからいなくなれば、通訳自身も契約満了になる可能性があります。その場合、別クラブに雇用される機会を新たに探さなければなりません。語学力を活かした仕事に就きたいのであれば、有名大学を卒業して、普通に就活して大企業に入れるような人材は、職の安定や報酬面を考慮しても、大企業に就職した方が良いです。海外支店の多いメーカーや商社に就職すれば、海外を相手に語学力を発揮したり、海外駐在したりするような機会は十分に得られます。懐がリッチになり、大学生時代はできなかったような毎週のアウェイ遠征もお金を気にせず楽しめるでしょう。そのような経験を経てなおもサッカークラブの通訳をやりたい夢が消えないのであれば、その時に挑戦すればよいと率直に思っています。ビジネスの場でマネジメント経験も少なからず積んでいるでしょうから、単なる外国語が上手な通訳以上の価値を発揮できる可能性もあるかと思います。
サッカークラブの通訳になる方法やキャリアの選択肢
チームスタッフの中でも、通訳は言語次第では多様な人材に広くアプローチする必要があるため、クラブが公式WEBサイトで求人を出すことが比較的多くあります。このような求人に応募することが通訳になるための王道でしょう。
キャリアの選択肢としては、サッカークラブで通訳をやり続ける人、コーチングライセンスを取得していたり海外の大学院で勉強したりした経験があれば別チームを含むコーチになる人、または、語学力を武器に代理人になる人など、キャリアプランによって様々です。特に、一度サッカー業界に浸り、チームスタッフとして様々な監督やコーチの方々、もしくは選手経由で代理人の方々と知り合えることは、その後のキャリアに繋がります(現役時代にお世話をした選手が母国でエージェントに転身するなんてことはよくあります)。
さいごに
普段割と花形的な通訳業務のみをイメージして相談に来る方が多いため、少し脅かすような内容になってしまったかもしれません。まずは厳しい現実を理解していただくことを本稿の主旨にしました。
もちろん、通訳をやっていて良いことややりがいは多々あります。通院やリハビリに長く付き合った末にその選手が試合で活躍してくれたら報われた気持ちになりますし、サポートしていた選手が引退してもたまに日本に帰ってきて、クラブハウスやスタジアムで再会したときには、昔の旧友に会うような懐かしさを覚えます。このようなやりがいやご自身のキャリアの選択肢を踏まえて、絶対にサッカークラブの通訳になるんだという断固とした覚悟があるのであればぜひ挑戦してください。覚悟をもって業務に当たれば、必ずや上記のようなやりがいを感じることはできると思います。
さて、本稿をもって、全9回にわたってご紹介した「サッカー×ビジネス」キャリアの築き方は完結となります。長きにわたって読んでくださった皆様に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。