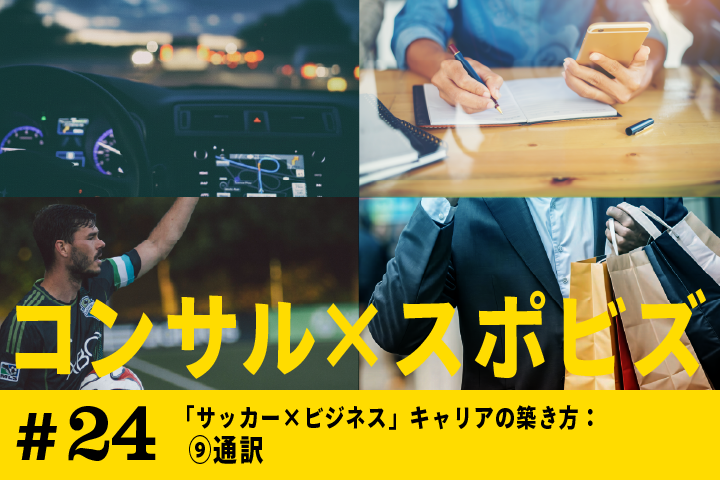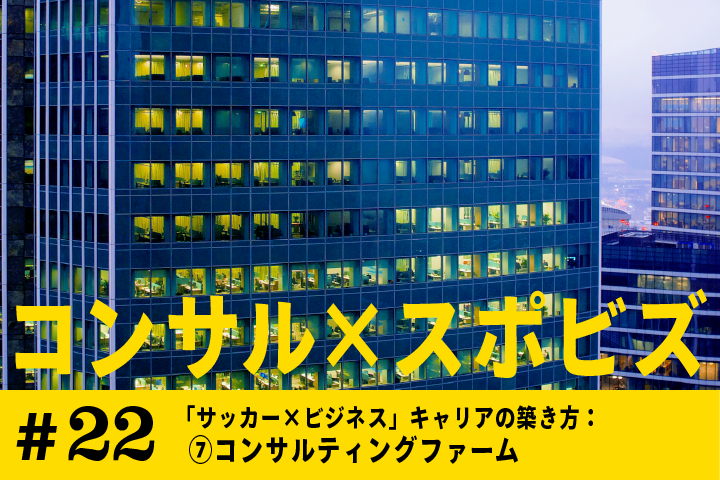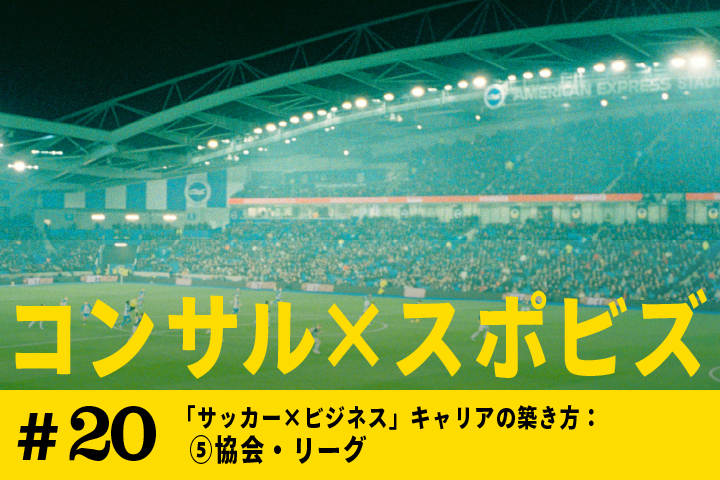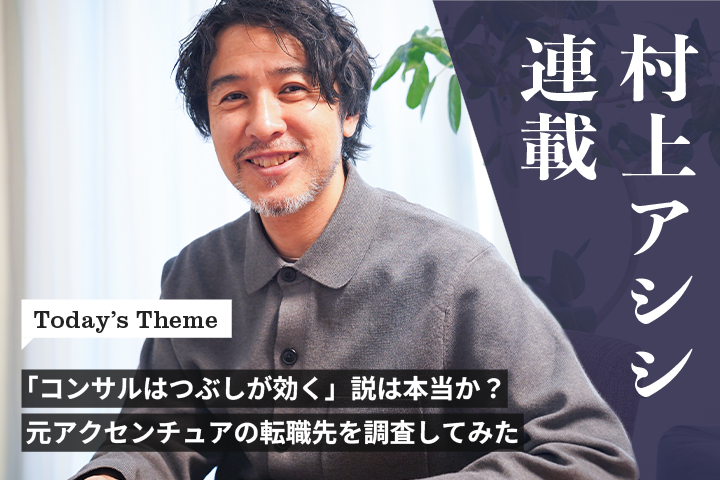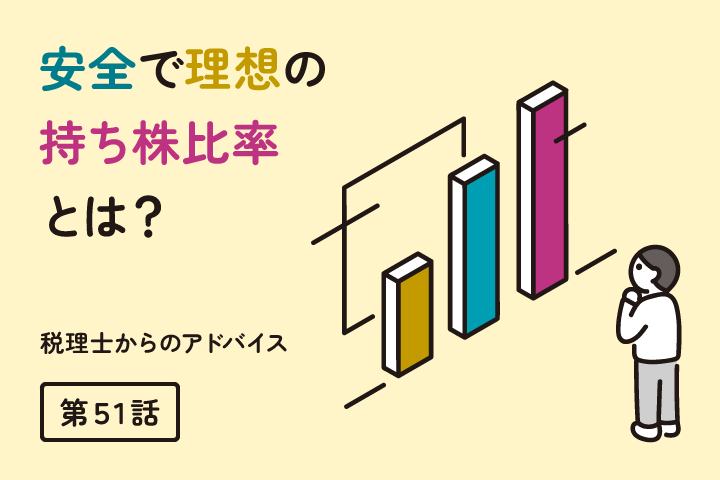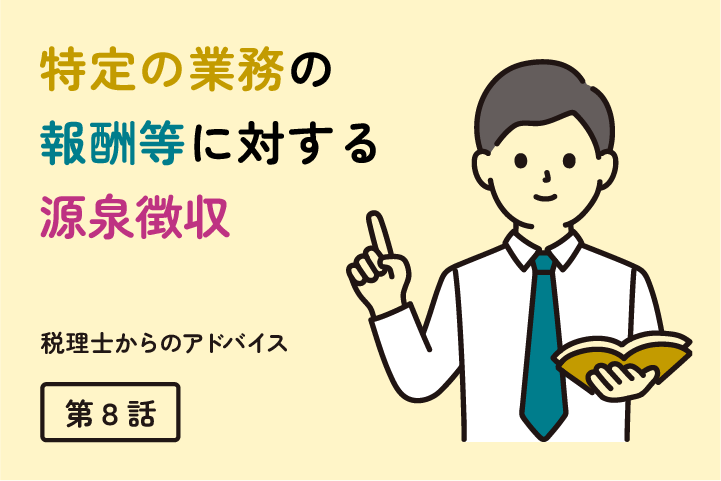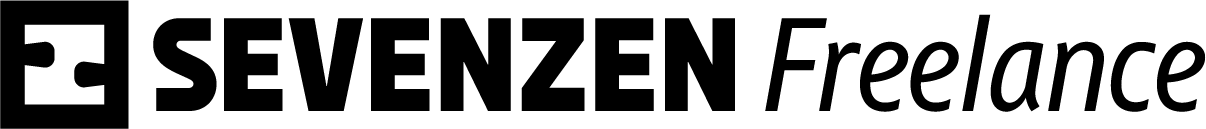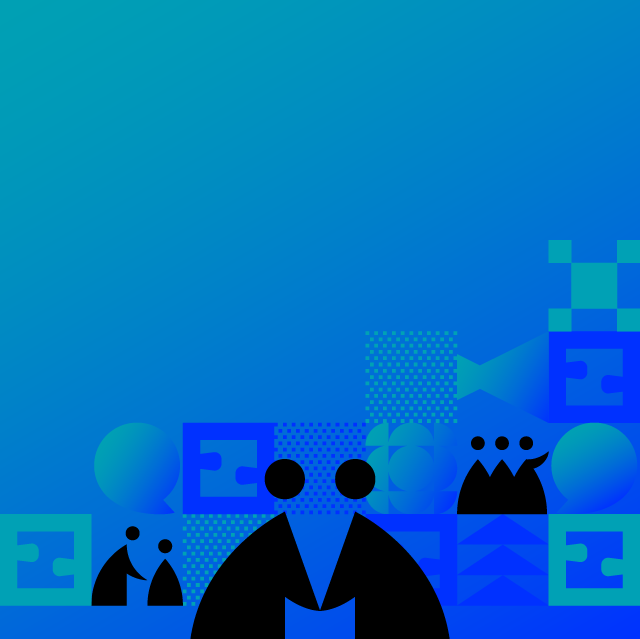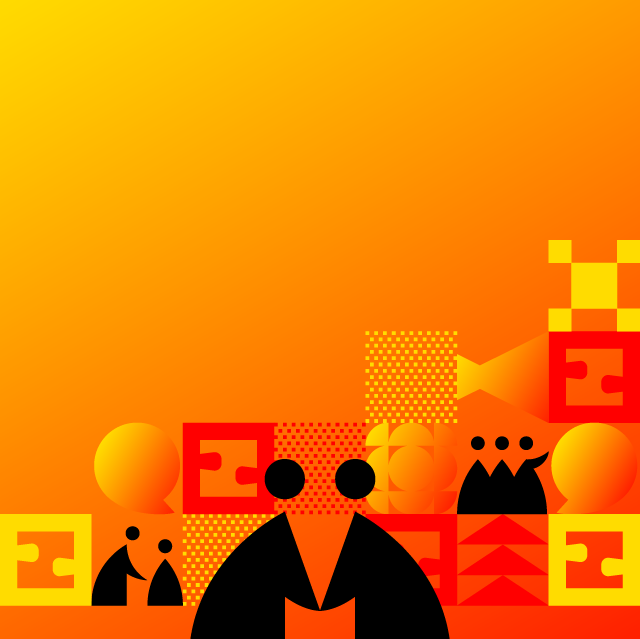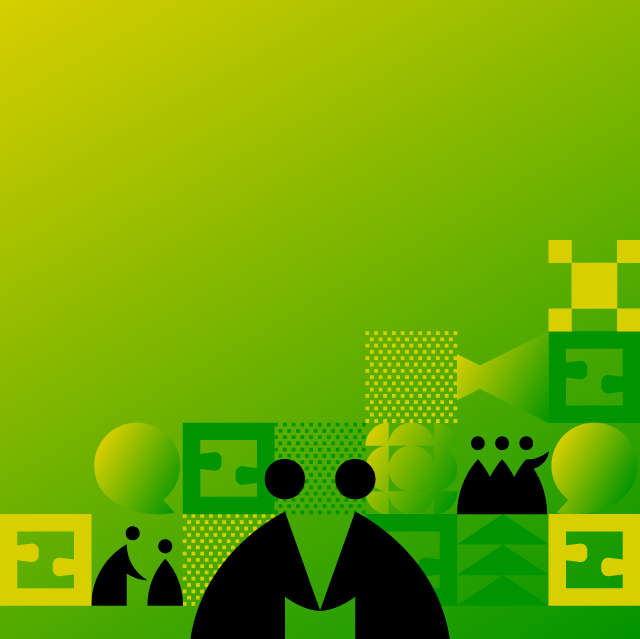「サッカー×ビジネス」キャリアの築き方の連載において、第1-6回目までは、サッカービジネスのど真ん中に位置する「スポーツ部門(強化部)」とそれに直接的な影響を与え得る周辺産業におけるキャリアについて解説しました。
第7回からは3回に分けて、自分自身のこれまでのキャリア(大学の外国語学部⇒コンサルティングファーム⇒個人事業主として独立・プロサッカークラブと契約)を踏まえ、特に読者の皆様に経験則をお届けしたい「コンサルティングファーム」「フリーランス/個人事業主」「通訳」というキャリアについてご紹介いたします。
(私のこれまでのキャリアについては、こちらの記事でもお話しています。)
第8回目は「フリーランス/個人事業主」について、ご紹介いたします。
本題に入る前に、本連載の「前提」を振り返ります。
※本連載の全ての記事において、冒頭に「前提」を明記します。記憶が新しい方は読み飛ばしていただいて構いません。
連載の前提
■内容
「サッカー×ビジネス」というキャリアの築き方について、スポーツ部門(強化部)の周辺ステークホルダーから考えられる職種、就職の方法、得られる機会、注意点、ネクストキャリアの可能性など
■ターゲット
国内外の有名大学を卒業予定で将来はサッカー/スポーツビジネス業界でキャリアを築いていきたい学生、または、その延長にいる若手社会人
■コンセプト
単なるお仕事図鑑ではなく、スポーツ部門にいながら感じた現場のありのままの情報を届けること(情報の全体感より深さを優先)
上記を前提として、本文をご一読いただけると幸いです。
「サッカー×ビジネス」のキャリア:⑧フリーランス/個人事業主
自分自身の経緯
私は前職のコンサルティングファームでは正社員として働いていましたが、プロサッカークラブに強化部スタッフとして転職するタイミングで会社員を辞め、個人事業主として独立しました。個人事業主に切り替えた背景には、強化部スタッフの多くが選手やチームスタッフと同じ「プロフェッショナル契約」で働いているという業界慣習があります。これらいわゆる競技サイドの人間は、結果で評価される世界であるため、その多くが会社と業務委託契約を結び有期で仕事をしています。私自身も、会社員を辞めるというのは初めての経験だったので、オファーをいただいた最初は悩みました。ただ、よくよく考えると、正社員でなくてはならないこだわりが特に見当たりませんでした。それよりも、この延長線上に自ら目標としていた起業があることは理解できたため、独立への抵抗感は拭えました。
その後、強化部で4年ほど個人事業主として業務を行い、2024年2月に本事業を法人化、現在は自社とクラブ間で業務委託契約を結んでいます。
プロサッカークラブにおける雇用形態
プロサッカークラブでは、社員のようにほぼフルコミットで働くスタッフであっても雇用形態が一律ではありません。事業サイドは社員(契約社員を含む)が中心ですが、競技サイドは強化部を含めて業務委託が大半です。一部、事業サイドであっても、広報や競技運営など「競技サイド寄り」の職種では、個人事業主で働く方も一定います。また、営業職で成果報酬型の勤務を希望する場合など、自社の報酬テーブルに則らない業務委託で働いている方もいます。次に詳述するように、会社員としての安定を手放す覚悟こそ必要ですが、自らの職種に対して専門性を持ち、会社に対して価値を発揮できる確信があるようであれば、挑戦しがいはあると考えます。
フリーランス/個人事業主になる際の注意点
真っ先に思い浮かぶリスクは、売上の安定性に欠けることでしょう。正社員であれば労働基準法に守られるため、原則としては解雇つまり職を失うことはありません。一方で、個人事業主の業務委託は有期契約になります。契約の定めの中で、「契約満了のXXヶ月前までには両者更新に関する議論をする」といった主旨の条項を設定することが一般的なので、即刻契約がなくなり明日から収入がありませんといった事態は、契約解除事由に抵触しない限りは基本的に発生しないでしょう。そうはいっても、1社の契約先にフルコミットであり、もし契約更新がない旨を会社から言い渡された場合は、当該契約が残るわずかな期間に、次なる契約先を見つけなければなりません。
契約更新や報酬の金額交渉も全て自ら行います。競技サイドの中でも選手や一部の監督コーチにはエージェントがつくのが一般的ですが、強化部や事業スタッフがエージェントをつけるのは一般的ではありません。契約更新のタイミングで、ともに仕事を担ってきた担当者やその先の管理部門、場合によっては役員とお金の話をしなくてはならないのは、気も遣いますし喜ばしいものではないのが正直なところです。評価次第では、契約更新のタイミングで原契約の報酬からゼロベースで報酬金額が見直されることもゼロではありません(ただし、不当ではない範囲)。
その他の注意点として、社会保険の手続きや、確定申告、納税などを全て自ら管理しなくてはならない点が挙げられます。正社員であれば、社会保険や納税の手続きは、給与支払い時の折半や年末調整等を通じて、基本的には会社が全て整えてくれます。自分自身を振り返っても、会社員時代には納税金額やこれら手続きの負担を気にしたことはありませんでした。一方で、個人事業主になると、青色申告を含む開業届関連を始めとし、国民健康保険やその他社会保険への加入とそれら費用の支払い、また、年間の帳簿記録や期末の確定申告など、様々な煩雑な事務手続きを全て自分で行う必要があります。
ここまでの内容を読むと個人事業主への挑戦が億劫になるかもしれませんが、現在はfreeeのような専門知識がなくても使いこなせる会計ソフトで開業届出や確定申告もできますし、オンラインでスポット税理士を探せるようなサービスも普及しているので、手続き関連は初年度に慣れてしまえば簡単でしょう。したがって、このような事務手続きの負荷は本質的なリスクにはならず、売上の源となる顧客/取引先の確保こそが、個人事業主として生計を立てる上で最大の争点になります。
スポーツ業界ならではのフリーランス/個人事業主になるメリット
そもそもプロ選手やチームスタッフの多くが個人事業主であるため、プロスポーツクラブ側には業務委託への理解と受け入れ体制が整っているように感じます。フルコミットでの転職活動をする場合、一般企業への就職であれば正社員が前提ですが、プロスポーツクラブでは社員(契約社員を含む)か業務委託かを選択できる場面が多く発生するものと想定しています。社員としての報酬テーブルに乗っかれない方、柔軟な複業に挑戦したい方、フルコミットといえど業務特性上場所や時間に縛られたくない方などは、個人事業主として業務委託契約を結ぶことがあるでしょう。ちなみに、プロスポーツクラブの業務特性上、事業サイドであっても業務委託を選択する背景については、こちらの記事をご参照ください。
このような、個人事業主としてフルコミットでのスポーツ業界への転職であれば、前述の「売上の源となる顧客の確保」が、対1社ではありますが最初から実現するのは大変ありがたいことです。会社員からゼロベースで独立・起業するよりも、まさに会社員の延長線に近い形で、フリーランス/個人事業主に挑戦できます。個人的な経験からも、これこそがスポーツ業界で個人事業主になることの最大のメリットだと感じています。
その中でも、JFAやJリーグは正社員採用が中心ですが、プロスポーツクラブの採用では業務委託契約が提示・提案されることも多く、契約社員と業務委託を組み合わせた柔軟な採用が行われています。または、そもそもの採用要件が業務委託契約であるケースもよく見られます。スポーツ業界に特化してキャリアを築くんだという強い覚悟や信念がある方は、前述のリスクを負ってでも個人事業主としてプロスポーツクラブに入り、現場で実績や能力・経験を積み重ねる選択肢は大きなチャンスに繋がると実感しています。ただし、そのような選択は自らに専門性があることが前提です。発揮できる価値がないのに個人事業主を選択するのはリスクでしかありませんので、特に事業サイドでの勤務については一定会社員として経験を積んだ後の中途採用で選択するのが現実的でしょう。
まとめ
プロスポーツ業界でフリーランス/個人事業主として働くことは、不確実性と隣り合わせである一方で、自分自身の専門性をダイレクトに取引先や社会の価値に転換できたり、柔軟な働き方ができたりと、魅力的な側面も大い感じられるキャリアパスでしょう。本コラムが読者の皆様にとって参考となり、自分らしいキャリア選択ができるその一助となれれば幸いです。