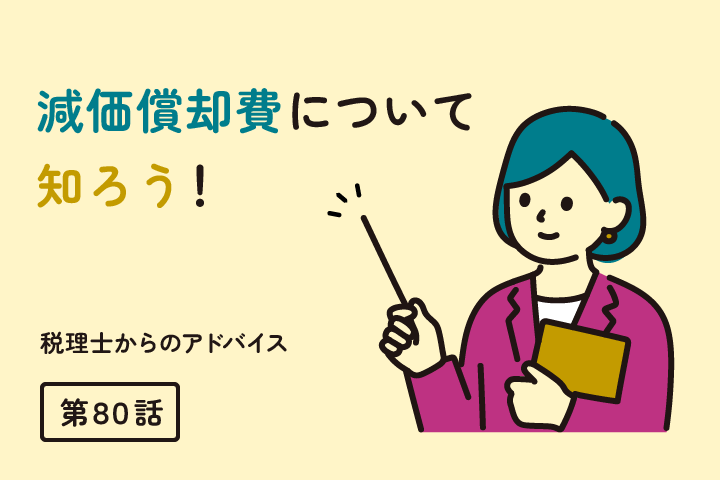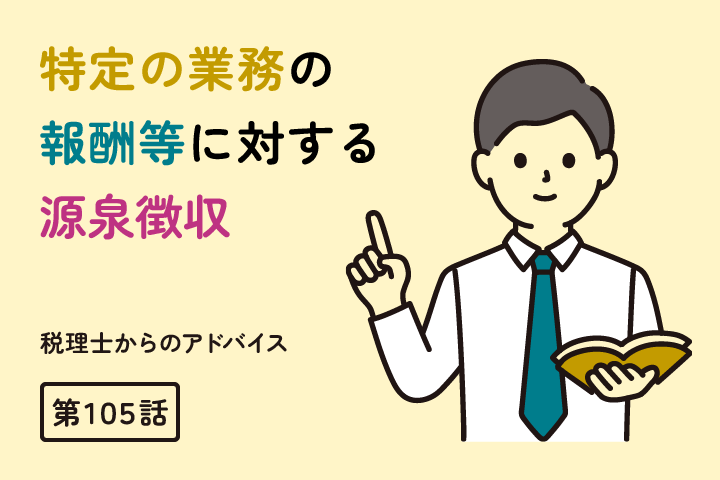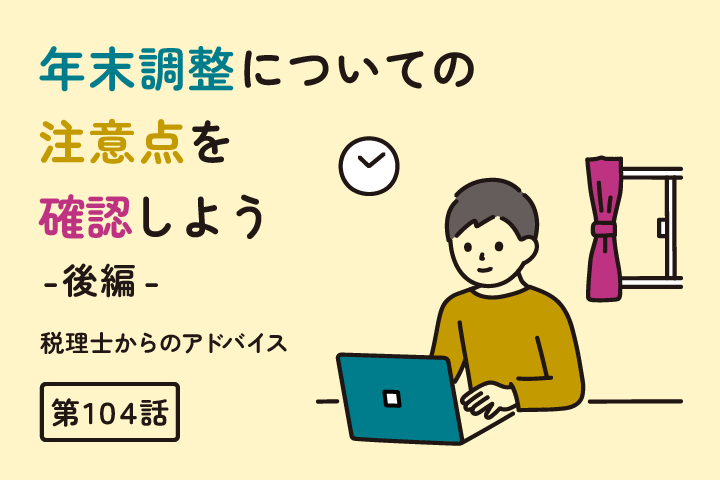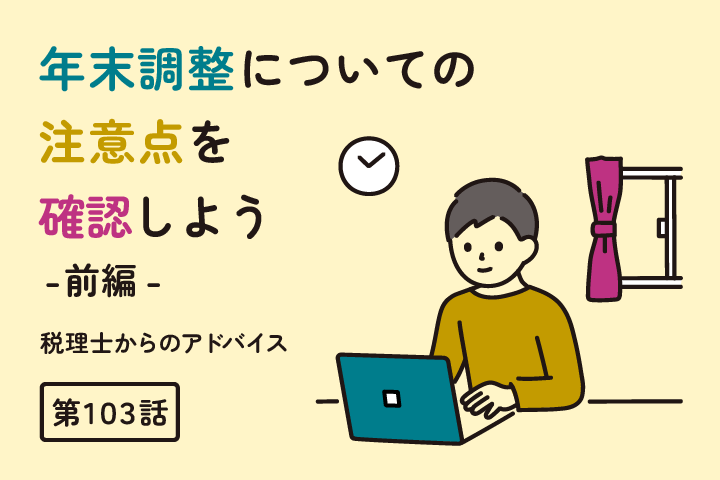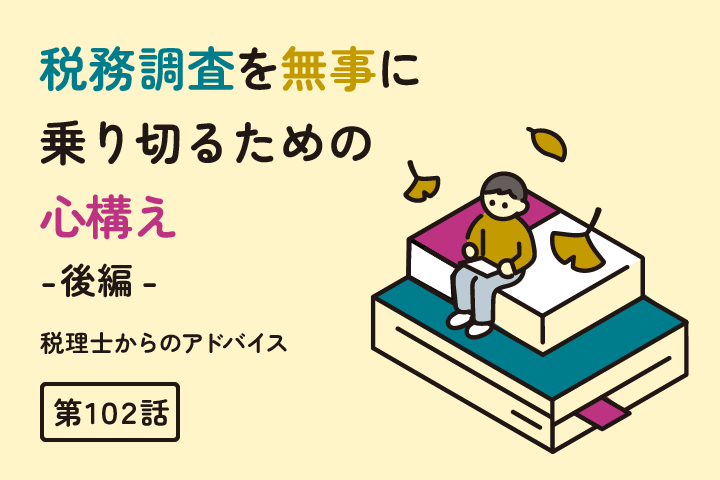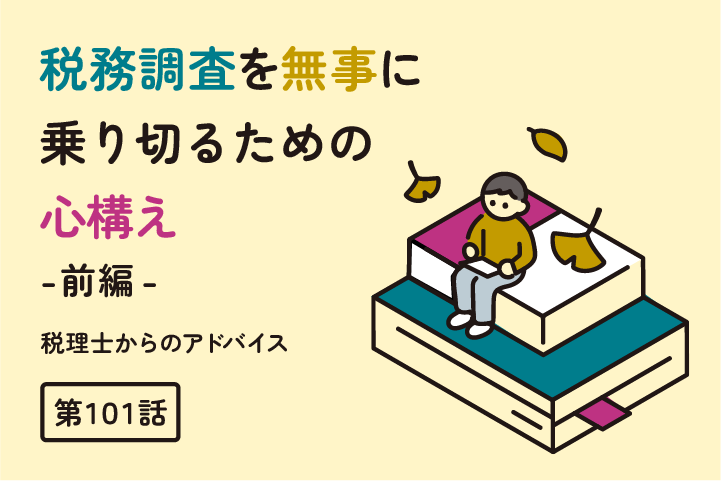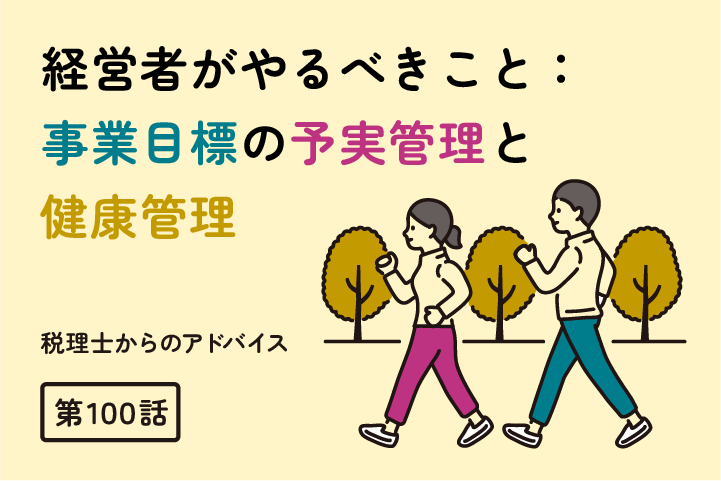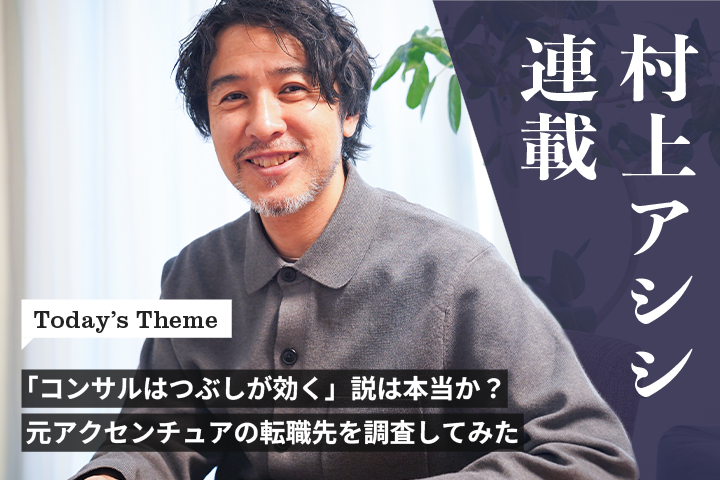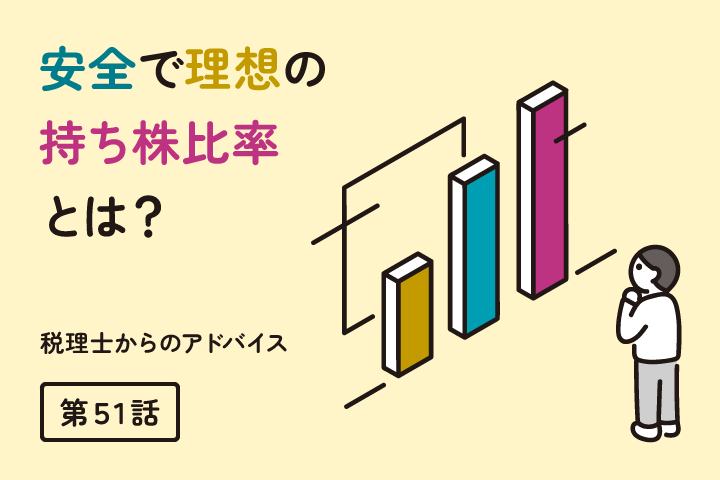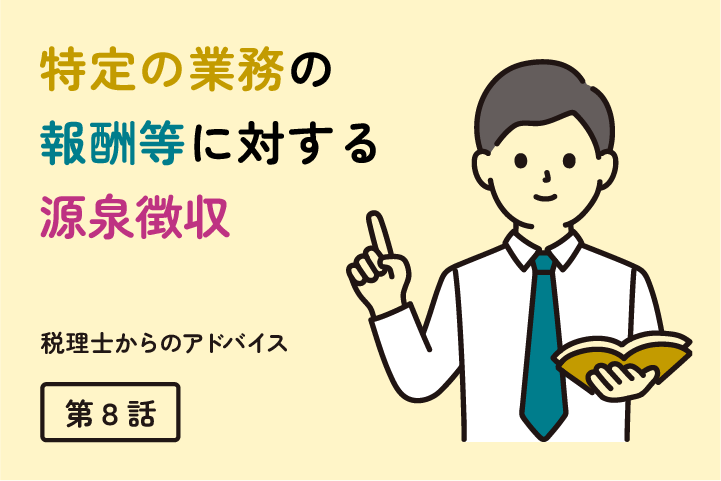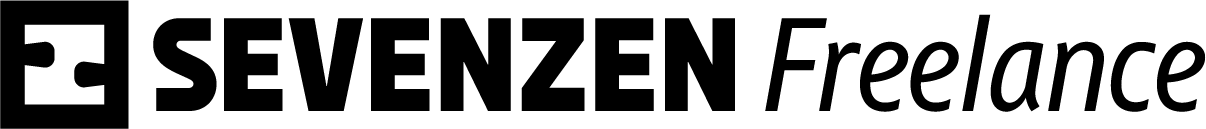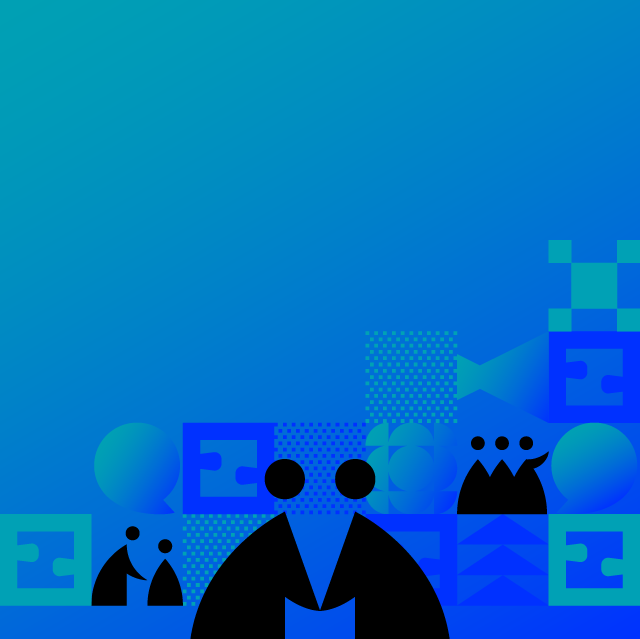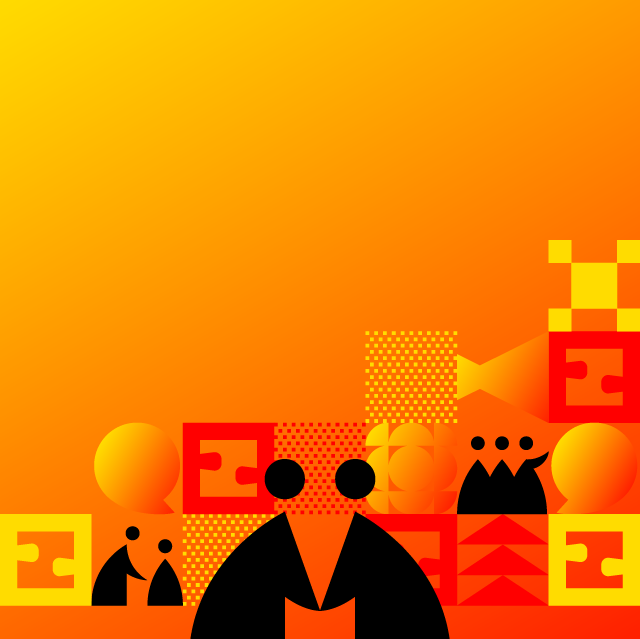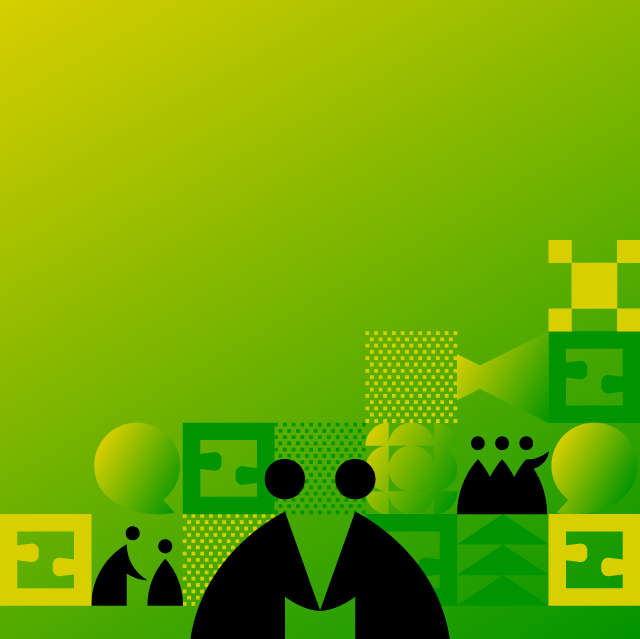簿記を習った方は知っている知識ですが、初心者向けに減価償却費について説明します。
定額法と定率法
例えば、3月決算で、4月1日に120万円の車を購入(納車)した場合、その購入した期に全額(120万円)経費として落として良いか?を考えます。
1年で壊れる車は無いと思います。そこで、会計上の考え方は、使える期間で按分して経費計上する事が基本です。
使える期間(耐用年数)を6年とすると、120万円÷6年=20万円を毎期、減価償却費として経費計上出来ます。
この考え方の計算方法を定額法と言います。建物に使われる方法です。
別の減価償却費の計算方法もあります。最初多めに計上され徐々に少なくなる方法です。
例えば、初年度30万円、2年目25万円、3年目15万円を減価償却費として経費計上します。トータルの減価償却費合計額は、定額法と同じです。この考え方の計算方法を定率法と言います。車両については、定額法でも定率法のどちらでも選べます。定率法を選ぶ場合は、黒字企業では早めに償却費を計上したい場合に選択すると良いです。
個人で届出書を提出していない場合は、定額法(法定償却方法という)。
法人で届出書を提出していない場合は、定率法(法定償却方法という)。
注意点としては、建物は定額法しか選べません。また、個人の場合で、車両の減価償却方法を定率法で計算したい場合は、税務署へ届出を出さないといけません。

計算する上で大切な項目
減価償却費を計算する上で大切な項目があります。
(実務では、減価償却費を計算するソフトにデータをいれれば、計算してくれます。)
- 取得価額
車両を購入した場合には、カーナビ代も含めます。保険料やリサイクル預託金は含めません。この金額が間違っていると正しい計算が出来ません。 - 耐用年数
実務では、税務署で規定している耐用年数を使います。例えば、普通乗用車であれば、6年です。 - 事業供用日
専門用語ですが、取得日と違います。実際に使える様になった日です。機械装置については、ちゃんと稼働した日(試運転完了)からとなります。決算日近くの場合には、今期なのか来期なのかを注意してください。減価償却費の経費計上は、取得日では無く、事業供用日からとなります。 - 償却方法
定額法や定率法の事です。
1から4の項目を整理し、減価償却費を計算するソフトにデータを入力すれば、その期の計上出来る減価償却費が分かります。
例えば、車両を購入して減価償却費の計上限度額が20万円であれば、個人の場合は、強制的に20万円を計上。法人の場合は、0から20万円を任意計上出来ます。
以前のコラム(6話)でお話していますが、新品の機械装置を購入した場合には、特別償却か税額控除を使える場合があります。
・特別償却とは
通常の減価償却費に、プラスして減価償却(例えば、取得価額の30%)する事。
課税の繰延である。(減価償却の合計は、同じ。償却するスピードが違うだけ)。
・税額控除とは
法人税(所得税)からダイレクトに、税額(取得価額の7%)を引いてくれる事。税減免。
事業供用日で、使える期を判断します。節税をする時の大切な知識の一つとなります。ご参考まで。
それでは。良い一日を!!